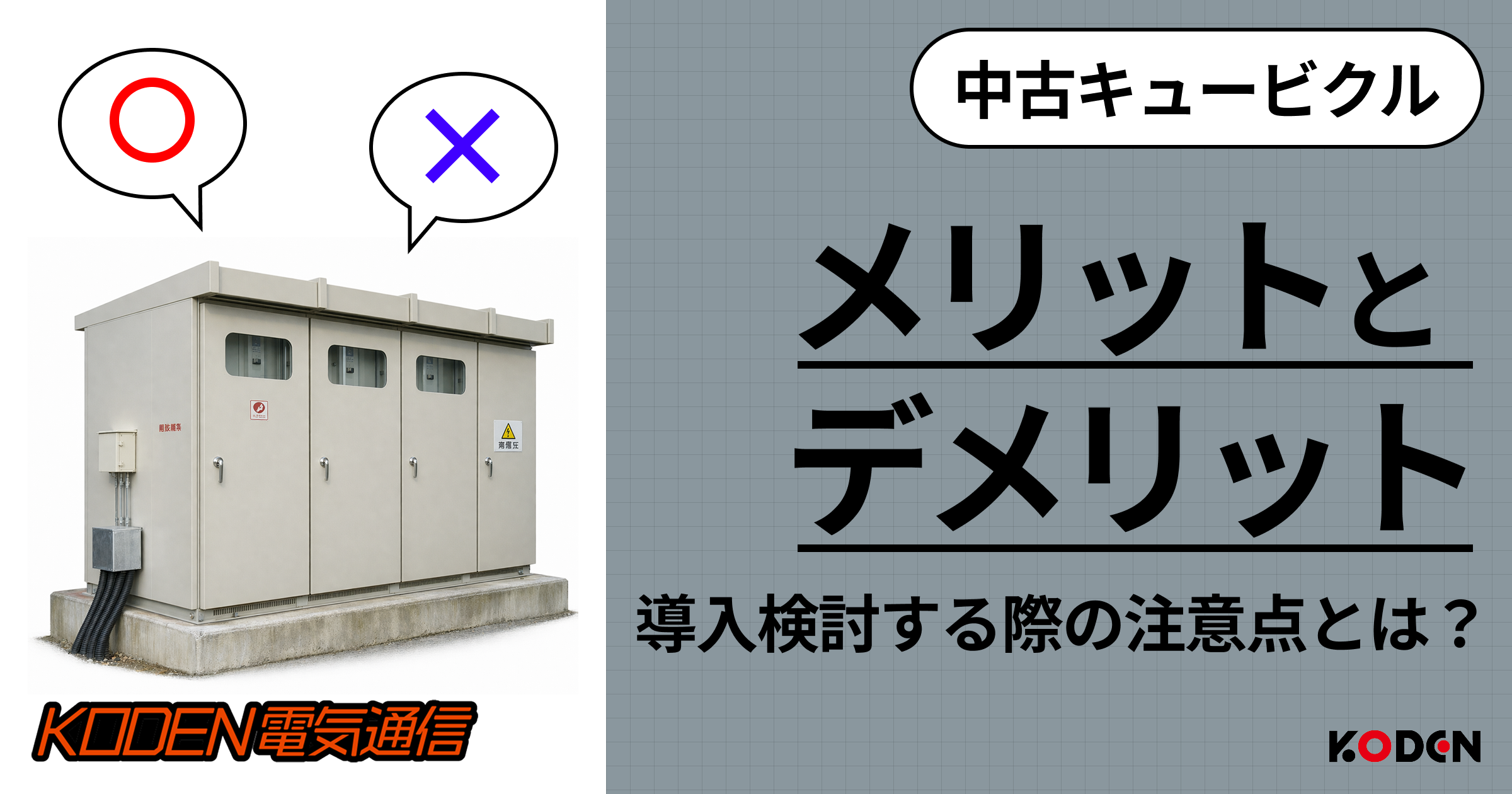【高圧ケーブル更新工事の手順】結局、お客様は何をすれば良いのか?[東京電力管内]
カテゴリー:
タグ:
更新日:2026年2月5日
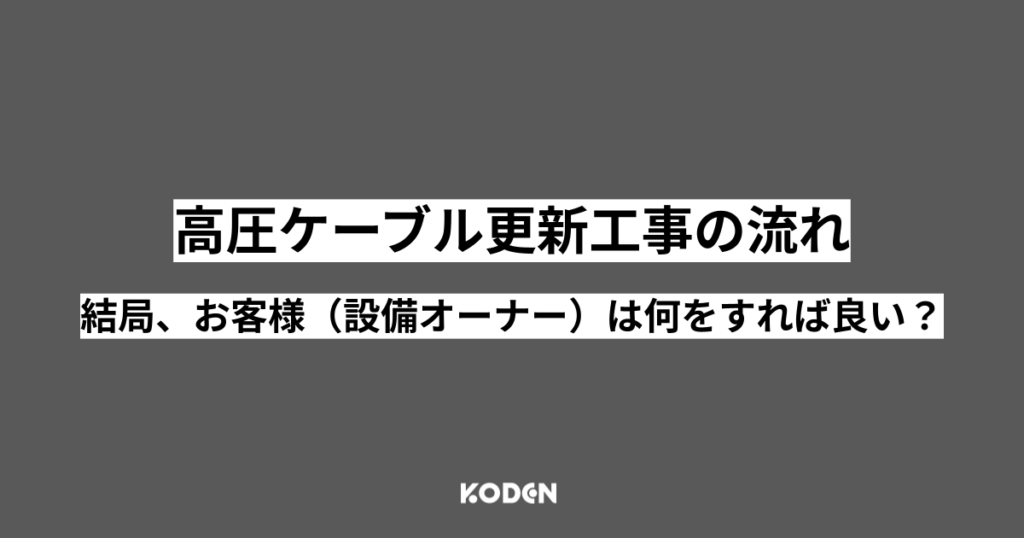
老朽化したケーブルは、絶縁低下や発熱・地絡のリスクを高め、思わぬ停電や設備トラブルの原因になります。とくにキュービクル〜需要家側盤までの高圧・低圧ケーブルは建物の“血管”にあたる重要部分です。計画的な更新で、安全・安定供給を守ることができます。
本記事では、「❶事前手続き」→「❷工事準備」→「❸工事実施」→「❹後日対応」の4ステップで、高圧ケーブル更新工事の全体像とオーナーが何をすべきかを分かりやすく解説します。
▼関連記事はこちら
監修

❶事前手続き
1)お問い合わせ【お客様+電気工事会社】
まずは、電気工事会社へ工事の「相談・問い合わせ」を行います。より正確で迅速に工事を遂行するため、問い合わせの際に、オーナー様側でご準備いただきたい主な書類・情報は以下のとおりです。
- 年次月次点検表の写し
電気保安協会や主任技術者からの年次点検報告書があればご用意ください。過去の指摘事項や不具合履歴が分かると、高圧ケーブル更新工事の仕様を検討する際に役立ちます。 - 電気料金の請求書の写し(契約情報の確認用)
契約情報の確認を行います。工事が始まるまでにご準備ください。 - 建物・電気図面(可能であれば)
設備の必要情報が回路図とともに記載されています。ご準備が可能でしたら、現地確認もスムーズに行えます。
2)現地確認(立入範囲・立会い)の実施【電気工事会社+お客様】
お問い合わせ後、担当者が実際の設置場所や既存設備の現地確認を行います。現地確認でチェックされる主なポイントは下記のとおりです。
- ケーブルの敷設状況の確認
ケーブルの経路、敷設方法、架空配線、ケーブル末端処理部分などについて確認します。
- 工事計画・作業環境に関する確認
ケーブルや工具などの搬入搬出経路、クレーン使用の可否(通路の幅・段差等)、大型重機の車両の乗り入れに際する駐車場の確保や、作業スペースの有無とその広さなどを確認します。
- 安全確保に関する確認
高所作業の墜落防止対策の確認(屋上の場合)、隣接する建物や設備(作業に影響を与える障害物)の有無、作業員の導線確認を行います。
現地確認の際には、お客様の立会いが必要です。必要事項のヒアリングが完了しましたら、最初と最後のみのお立会いで問題ございません。
主任技術者の立会いは原則不要ですが、施設の管理状況により必要な場合は当社からご相談します。
※恒電社の場合、現地確認の費用はいただいておりませんのでご安心ください。
3)見積書・工事計画書の提出【電気工事会社】
現地確認で得た情報に基づき、工事会社は高圧ケーブル更新工事の見積書を作成します。一般的に見積書提示までは調査完了から1〜2週間程度です。見積書には以下の内容が明記されます。
- 費用構成の例
ケーブルの長さやサイズ、敷設ルートの難易度(露出/天井裏/シャフト/地中)、端末処理の箇所数などが内訳として示されます。特殊条件による割増費用や道路使用許可の要否、仮設設備(停電不可時の発電機 等)があれば項目に含まれます。 - 所要時間の目安
工事は通常1日程度、停電は4〜8時間程度を計画します(現地の条件で前後します)。通常、停電作業日は1日と想定されますが、天候等で順延する場合の予備日の設定を行う場合もあります。 - 夜間・休日工事
電気工事会社によって対応可否(別途費用の発生)が異なります。テナント営業やオフィス稼働への影響を最小化できます。
オーナー様は提示された見積書の工事範囲と金額を十分に確認しましょう。不明な費用項目があれば施工業者に質問し、納得したうえで次の意思決定に進みます。
また、恒電社ではこのタイミングで工事計画書を作成し、送付する場合もございます。ご希望の時間帯をヒアリングした上でスケジュール表を作成しますが、受注前(電力申請前)のため、未確定の段階です。計画書には、他にも工事の概要、工程表、作業手順、安全対策、緊急時対応などが記載されます。
4)電気工事会社への発注・契約手続き【お客様+電気工事会社】
工事内容・見積金額にお客様が合意いただけたら、電気工事会社に正式発注します。一般的には見積書に発注サインをし、工事請負契約書を取り交わす形です。ここで契約が成立したら、以降は工事会社が主体となって電力会社との各種手続きや工事準備を進めていきます。
※費用を抑えたい場合は、施設メンテナンス会社や建設会社など複数社を通さず、電気工事会社へ直接発注していただくことを強くお勧めいたします。
❷工事当日までの準備
5)東京電力への各種申請【電気工事会社】
契約が完了したら、「東京電力への工事申込」を正式に行います。通常、この手続きは電気工事会社が代理で行います。工事申込時には、以下の資料が東京電力に提出されます。
- 工事申込書(所定様式)
- 受電設備の単線結線図(更新後の新設備図面)
- 構内配置図(キュービクル設置場所や電力引き込み点が分かる見取図)
- 現地写真(設備周辺の状況が分かるもの)
東京電力側で申込内容の確認・審査が行われ、問題なければ受付が完了します。
6)工事日程の決定【三社】
工事日程は、電気工事会社が旗振り役となり、以下のメンバー間で調整されます。
- 東京電力パワーグリッド
- 電気工事会社
- お客様(or テナント)+主任技術者
三社の要望を踏まえ、「○月○日○時〜○時に停電し工事実施」という計画が決まります。停電時間は工事内容によりますが、半日程度(4〜8時間前後)で完了するよう計画されることが一般的です。もちろん工事範囲が大きければ終日停電もあり得ますが、通常は影響を最小限に抑えるため、人員増強や並行作業でできるだけ短時間で復電できるよう工夫します。
※なお、工事日程の調整には思いのほか時間がかかります。ビル利用者の都合や東京電力の作業枠の制約などで希望通りの日程を確保するには数か月先になるケースもありますので、計画段階から「◯月中には実施したい」など出来るだけ早めに調整することをおすすめいたします。
7)各種許可申請【電気工事会社】
必要に応じて行政への許可申請も行います。代表的なものが道路使用許可です。クレーン車を道路に一時駐車して吊り作業を行う際は、警察署から道路使用許可を得なければなりません。申請手続きは工事会社が代行しますが、オーナー様には道路使用料などの実費負担が発生するケースもあります。
その他、鉄道や高度な安全管理が求められる施設の場合は事前にリスクアセスメントを行い、計画書に反映します。関係各所への届け出(消防署やビル管理会社への作業通知など)が必要な場合も、この段階で漏れなく済ませておきます。
8)テナント・近隣住民への通知【お客様】
工事日が正式決定したら、少なくとも数週間前には、建物のテナントや利用者、周辺の関係者へ停電と工事の予定を通知してください。高圧ケーブル更新工事は停電を伴うため、事前に入居者や関係者へ周知徹底することが不可欠です。具体的には、以下のような対応を行います。
- 告知文の配布
停電日時や作業内容を記載した「停電のお知らせ」文書を作成し、テナント各社やビル利用者に配布します。
- 協力依頼
テナントには停電中の営業調整(事前の告知や休業検討)、重要機器の遮断(エレベーターを停止位置に移動、PCやサーバのシャットダウン)など協力を依頼します。マンションの場合は住民へエレベーター停止時間を知らせ、停電中は感電防止のため分電盤やコンセントに触れないよう注意喚起します。
9)当日の入室・鍵手配【お客様】
- ルート上の機械室・シャフト・屋上等に入室できるよう鍵・カードのご準備をお願いします。
❸工事実施
10)工事日当日(工事作業前)
いよいよ「工事日当日」です。工事作業前の流れは以下のとおりです。
- 朝の打ち合わせ(朝礼):工事関係者(東京電力作業員、電気工事会社、主任技術者、お客様設備担当など)が現地に集まり、停電時刻や作業手順を確認します。
- 安全措置の確認:作業者は保護具(ヘルメット、絶縁手袋、安全帯等)を着用。高圧側回路にアースを装着し、誤送電があっても作業者に電気が流れないよう対策します。現場には立入禁止表示を掲示し、主任技術者や現場責任者が安全管理を行います。
- 停電措置の実施:定められた時刻に東京電力作業員が受電ポイント(電柱開閉器や引込遮断器)を操作して送電を遮断。お客様設備内も遮断器をオフにし、検電器などで無電圧を確認してから作業を開始します。
11)既設ケーブルの切り離し・撤去、新設ケーブルの布設・端末処理・結線【電気工事会社】
停電が確認されたら、既存ケーブルの撤去作業に取りかかります。
- 端子部を安全に切り離し、ルートに合わせて引抜・撤去。養生しながら搬出します。
既存ケーブルの撤去が完了したら、続いて新しいケーブルの据付です。工程は、撤去時の逆順になります。
- 既存ラック/ダクト/シャフトを利用、必要に応じて新設補強。
- 端末処理、ラベル表示、結線・締付トルク管理を確実に行います。
これで主な電気工事は一段落です。
12)試験(絶縁・耐圧・導通 等)の実施【電気工事会社+主任技術者】
新たに設置した高圧ケーブルは、送電再開前に法令で定められた使用前自主検査を行う必要があります。主任技術者が実施し、設備が安全に運用可能か確認する重要な工程です。主な試験項目は以下です。
- 絶縁抵抗測定
ケーブルや機器の絶縁状態が良好であることを確認します。 - 耐圧試験
高圧設備に所定の試験電圧を一定時間加え、絶縁破壊や放電が起きないかを確認します。 - 相回転確認
高圧ケーブルをつなぎ替えた後に機械が正しい方向に動くように、電源の相(R・S・T相)が正しく接続されているかを確認します。
検査は主任技術者が責任を持ち、記録を残すのが原則です。電気工事会社が試験器を用意してサポートする場合もあります。すべての試験に問題がなければ合格です。
13)電力会社の復電作業・負荷確認【東京電力】
試験結果に問題がなければ、電力会社の担当者により、停止していた高圧送電を再開します。
作業員が系統ごとに順次投入し、電圧・電流・温度・異音/異臭の有無を確認します。全設備が正常稼働すれば復電作業完了となります。
送電再開にあたっては、まず工事会社・主任技術者から電力会社へ「復電準備完了」の連絡を入れます。電力会社作業員が安全を確認した上で所定の手順に従い開閉器を操作し、送電を開始します。その後主任技術者により安全を確認しながら順次復電操作を進めます。
当日の立会いについて
- お客様:終日の常駐が難しい場合は、停電開始時・復電時のみの立会いで問題ございません。
- 主任技術者:当日は立会いが必要です(安全な設置・検査のため)。
高圧ケーブルの施工事例
❹後日対応
14)報告書の提出【電気工事会社】
全ての工程が完了したことをお客様へご報告し、設備一式をお引き渡しします。試験成績書、施工前後写真、更新後の系統図(該当箇所) 等などの書類も併せて提出いたします。
ここに至るまで長期間にわたる工事となりましたが、高圧ケーブルの老朽化によるリスクを低減し、安心してお使いいただける状態となります。
15)工事費用+主任技術者への立会い費用のお支払い【お客様】
工事完了後の費用のお支払いについては、電気工事会社への工事代金のお支払いがあります。
見積り・契約時に取り決めた支払条件に従い、請求書の期日までに指定の口座へ工事費用をお振込みください。
また、主任技術者への工事立会い費用は、通常の月次・年次点検料に含まれない場合が多いため、事前に確認しておくことが望ましく、必要に応じて別途費用を支払う必要があります。
【まとめ】
以上が、東京電力管内で実施される高圧ケーブル更新工事の主な流れと、お客様側で取り組むべき事項です。
事前準備から後日の対応まで順を追って見てきましたが、高圧ケーブル更新は「停電」や「入室制限(許可)」など、調整ごとが多い工事です。専門的で関係者も多いため大変そうに感じるかもしれません。しかし、信頼できる電気工事会社に依頼し、計画的に進めれば、お客様の負担は主に各種意思決定と連絡調整に集中できます。
古くなった高圧ケーブルを放置すると重大事故につながるリスクがあります。「いつかは交換しないと…」と悩んでいる方はぜひ早めに動き出すことをおすすめします。
設備更新によって安全性が向上し、テナントや従業員にも安心して電気をご利用いただけるようになるでしょう。今回解説したポイントを参考に、自社の状況に合わせた計画作りにお役立てください。
この記事を書いた人