【キュービクル更新工事の手順】結局、お客様(設備オーナー)は何をすれば良いのか?[東京電力管内]
カテゴリー:
タグ:
更新日:2026年1月16日
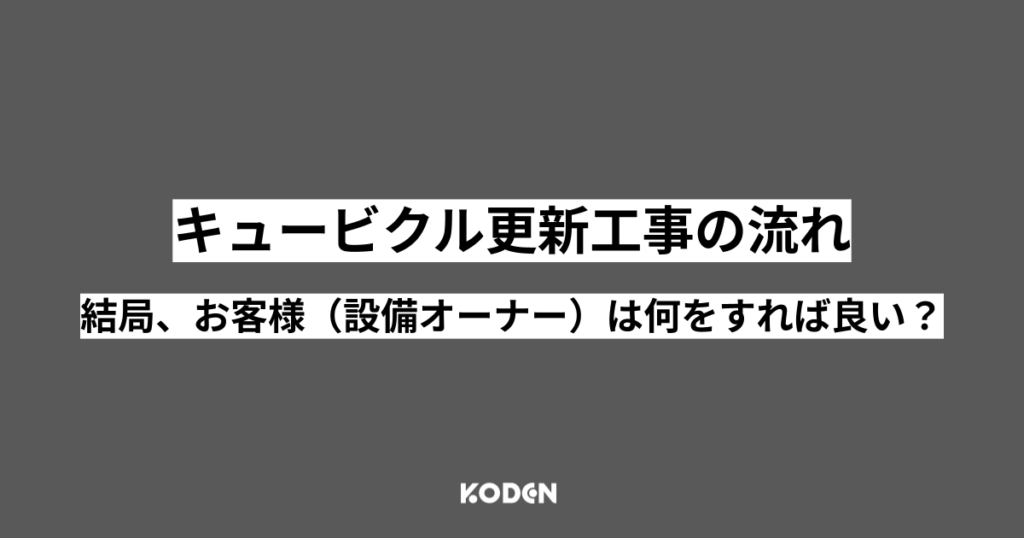
キュービクル(高圧受変電設備)は、電力会社から送られる約6,600Vの電気を建物で使う100V・200Vへ変換する設備で、敷地内にある小さな変電所のような役割を果たします。契約電力が50kW以上の施設には必須で、導入後約20年を目安に更新が必要です。
本記事では、「事前手続き」「工事準備」「工事実施」「後日対応」の4ステップに分け、キュービクル更新工事の流れとオーナーが何をすべきかをわかりやすく解説します。
監修

❶事前手続き
1)お問い合わせ・必要書類のご提出【お客様】
まずは、電気工事会社へ工事の「相談・問い合わせ」を行います。この際、お客様側で準備すべき主な書類・情報は以下です。
- 直近の「電気料金明細書」:
「お客さま番号」や契約電力などが記載されており、東京電力への申請に必要です。 - 設備の点検記録(月次・年次点検報告書):
外部の電気保安協会や主任技術者からの年次点検報告書があればご用意ください。過去の指摘事項や不具合履歴が分かると、新設備の仕様を検討する際に役立ちます。 - 受電設備の図面類:
現在の単線結線図や構内配置図がありましたらご準備ください。主任技術者が所有しているケースが多いため、ご不明な点などありましたら主任技術者へご確認ください。
2)現地確認の実施【電気工事会社】
お問い合わせ後、電気工事会社による「現地確認」が行われます。現地確認で確認される主なポイントは次のとおりです。
- 設置場所と搬入経路の確認:新キュービクル設置スペースの寸法や搬入・搬出経路をチェックします。大型トラックやクレーンが近くまで入れるか、通路の狭さや段差なども確認が必要です。
- 既存設備の状況:既存キュービクルの劣化状態や基礎の強度、周囲の障害物、引き込み電線の配置などを点検します。基礎が弱っている場合、補修工事が必要になることもあります。
- 受電容量や負荷の確認:現在の電力使用状況や将来を踏まえ、変圧器容量や契約電力を見直します。増減が必要ならキュービクルの設計変更を検討し、最適な容量を決定します。
※恒電社の場合、現地確認費用はいただいておりませんので安心ください。
3)見積書の提出【電気工事会社】
現地確認の情報に基づき、2週間ほどで電気工事会社から工事費用の「見積書」が提示されます。
キュービクル更新工事の費用は規模や条件によって大きく変動しますが、お見積りを左右する主な要素は以下のとおりです。
- キュービクル本体価格:電力使用状況、変圧器の容量など
- 工事費用:クレーン車・高所作業車の使用・夜間工事・狭い搬入口など特殊条件(条件が厳しいほど費用が高くなる)
- 付帯工事費用:老朽化した高圧ケーブル交換・基礎補修・古い設備の廃材処理(PCB含有油の有無確認など)※工事中に停電できない場合、仮設発電機や仮設受電設備の費用が追加
実際には上記の要因で幅がありますので、提示された見積内容について電気工事会社から説明を受けましょう。
4)電力会社との事前協議・工事負担金の“概算金額”の取得【電気工事会社】
見積書を取得と“同時”に、キュービクル更新にあたっては、東京電力パワーグリッドとの事前協議で「工事負担金の概算金額」を把握しておくことが欠かせません。
なぜなら電気工事会社での工事とは“別”に、東京電力会社側での工事が必要になるケースがあり、それらが「工事負担金」として工事実施前にお客様に直接請求がされる場合があるためです。
「工事負担金」:高圧受電の新設や契約容量の増加に伴い、電柱や配電線を新設・延長する場合に生じるお客さま負担分です。たとえば架空線では一定距離を超えた分に対し1mあたり約3,456円を負担します。地中配電設備の場合は掘削工事を伴い、さらに高額になる場合もあります。一般的には、架空線なら数十万円、地中線なら数百万円程度が目安です。
電気工事会社と契約後に思わぬ費用が後から発覚しないように、事前協議を行い、工事負担金(事前協議なので、あくまで概算金額)を把握した上で、工事をするかを検討をするべきです。
※事前協議は恒電社が代理で行いますのでご安心くださいませ。
※ただし、この段階で東京電力から提示されるのはあくまでも概算額に過ぎません。実際に東京電力へ支払う工事負担金は、工事申込書の提出後、正式に算定されます。7)で解説します。
5)電気工事会社への発注・契約手続き【お客様+電気工事会社】
工事内容・見積金額・電力会社への工事負担金(概算)にお客様が合意したら、電気工事会社に正式発注します。※費用を抑えたい場合は、施設メンテナンス会社や建設会社など複数社を通さず、電気工事会社への直接発注していただくことを強くお勧めいたします。
❷工事当日までの準備
6)東京電力への工事申込書提出【電気工事会社】
契約が完了したら、「東京電力への工事申込」を正式に行います。通常、この手続きは電気工事会社が代理で行います。工事申込時には、以下の資料が東京電力に提出されます。
- 工事申込書(所定様式)
- 受電設備の単線結線図(更新後の新設備図面)
- 構内配置図(キュービクル設置場所や電力引き込み点が分かる見取図)
- 現地写真(設備周辺の状況が分かるもの)
東京電力側で申込内容の確認・審査が行われ、問題なければ受付が完了します。
7)“正式”な工事負担金の確定、支払い【電力会社+お客様】
工事申込を受け、東京電力パワーグリッドは自社側で必要となる工事の設計が行われます。その上で「工事費負担金が正式算定」され、お客様に通知されます。
通知方法は、東京電力エナジーパートナー(小売会社)経由で請求書が郵送されるか、施工業者経由で知らされる形です。東京電力から「●月●日までに○○円をお支払いください」という案内が来ましたら、指定の支払期日までに振り込み等で納付します。
工事負担金のお支払いをしないとこの先のステップまで進むことができませんのでご注意ください。
8)工事日程の決定【三社】
東京電力への工事負担金の支払いが完了したら、いよいよ「工事日の決定」ができます。工事日程は、電気工事会社が旗振り役となり、以下のメンバー間で調整されます。
- 東京電力パワーグリッド
- 電気工事会社
- お客様(or テナント)+主任技術者
三社の要望を踏まえ、「○月○日○時~○時に停電し工事実施」という計画が決まります。停電時間は工事内容によりますが、半日程度(6~8時間前後)で完了するよう計画されることが一般的です。もちろん工事範囲が大きければ終日停電もあり得ますが、通常は影響を最小限に抑えるため、人員増強や並行作業でできるだけ短時間で復電できるよう工夫します。
※なお、工事日程の調整には思いのほか時間がかかります。ビル利用者の都合や東京電力の作業枠の制約などで希望通りの日程を確保するには数か月先になるケースもありますので、計画段階から「◯月中には実施したい」など早め早めに調整することをおすすめいたします。
9)各種許可申請【お客様+電気工事会社】
工事日が確定すると、電気工事会社が工事計画書を作成します。
当日の作業手順、担当者割り当て、安全対策、使用機材、停電手順、復電手順などを時系列でまとめたものです。これは社内用計画であると同時に、東京電力や官公庁への各種届け出の基礎資料にもなります。
電気工事会社が工事に付随する許認可も事前に取得します。代表的なものが道路使用許可です。クレーン車を道路に一時駐車して吊り作業を行う際は、警察署から道路使用許可を得なければなりません。
10)テナント・近隣住民への通知【お客様】
工事日が正式決定したら、少なくとも数週間前には、建物のテナントや利用者、周辺の関係者へ停電と工事の予定を通知してください。キュービクル更新工事は長時間の停電を伴うため、事前に入居者や関係者へ周知徹底することが不可欠です。具体的には、以下のような対応を行います。
- 告知文の配布:停電日時や作業内容を記載した「停電のお知らせ」文書を作成し、テナント各社やビル利用者に配布します。
- 協力依頼:テナントには停電中の営業調整(事前の告知や休業検討)、重要機器の遮断(エレベーターを停止位置に移動、PCやサーバのシャットダウン)など協力を依頼します。マンションの場合は住民へエレベーター停止時間を知らせ、停電中は感電防止のため分電盤やコンセントに触れないよう注意喚起します。
❸工事実施
11)工事日当日(工事作業前)
いよいよ「工事日当日」です。工事作業前の流れは以下のとおりです。
- 朝の打ち合わせ(朝礼):工事関係者(東京電力作業員、電気工事会社、主任技術者、お客様設備担当など)が現地に集まり、停電時刻や作業手順を確認します。
- 安全措置の確認:作業者は保護具(ヘルメット、絶縁手袋、安全帯等)を着用。高圧側回路にアースを装着し、誤送電があっても作業者に電気が流れないよう対策します。現場には立入禁止表示を掲示し、主任技術者や現場責任者が安全管理を行います。
- 停電措置の実施:定められた時刻に東京電力作業員が受電ポイント(電柱開閉器や引込遮断器)を操作して送電を遮断。お客様設備内も遮断器をオフにし、検電器などで無電圧を確認してから作業を開始します。
12)既存キュービクルの撤去、その後新設キュービクルの据付【電気工事会社】
停電が確認されたら、まず既存キュービクルの撤去作業に取りかかります。手順は以下の通りです。
- 高圧ケーブルの切り離し:引込側高圧ケーブルを受電部から外します。低圧側(変圧器二次側)の母線やケーブルも全て外し、古いキュービクルを完全に離線状態にします。
- 固定解除:キュービクルを基礎に固定しているアンカーボルトを取り外し、固着していればサンダーで切断。接地線も外し、箱体を持ち上げられる状態にします。
- クレーン吊り下ろし:クレーンやチェーンブロックで慎重に吊り上げます。重量が最大1.5トンにもなるため落下のないよう細心の注意を払います。周囲の障害物に接触しないようゆっくり移動。撤去後はトラックに積み込み、処分場へ運搬します。
既存設備の撤去が完了したら、続いて新しいキュービクルの据付です。工程は、撤去時の逆順になります。
- 新キュービクル搬入:あらかじめ搬入しておいた新品キュービクルを、クレーンや台車で設置場所まで運びます。クレーンが使える場合はトラックから直接吊り上げ、基礎上へ据え付けます。
- 据付・固定:所定位置にキュービクルを設置し、水平を確認後アンカーボルトで固定します。屋外型は架台上に設置し、架台ごとボルト締結。位置がずれないよう慎重に作業し、所定の場所にしっかり据付けます。
- 結線作業:高圧・低圧ケーブルを新キュービクルに接続します。高圧引込線を受電端子へ接続し、変圧器二次側の母線と建物側ブレーカーを結線。保護継電器の二次回路や接地工事も含め、施工図通りに確実に接続し、制御電源を入れて動作を確認。
これで主な電気工事は一段落です。
13)使用前検査の実施【電気主任技術者】
新たに設置したキュービクルは、送電再開前に法令で定められた使用前自主検査を行う必要があります。主任技術者が実施し、設備が安全に運用可能か確認する重要な工程です。主な試験項目は以下です。
- 絶縁抵抗試験:高圧・低圧回路それぞれの絶縁状態を測定し、規定値以上の絶縁抵抗を確保しているか確認します。
- 耐圧試験(交流耐圧試験):高圧設備に所定の試験電圧を一定時間加え、絶縁破壊や放電が起きないかを確認します。
- 動作試験:保護継電器や遮断器などの保護装置を試験装置で作動させ、設定どおりに動作・遮断するかを確認します。変圧器の無負荷試運転や二次電圧の測定も行い、正常値かチェックします。
検査は主任技術者が責任を持ち、記録を残すのが原則です。電気工事会社が試験器を用意してサポートする場合もあります。すべての試験に問題がなければ合格です。
14)電力会社の復電作業【東京電力】
試験結果が問題なければ、電力会社の担当作業員に送電再開を依頼します。
作業員が本線を投入し、新しいキュービクルへの受電が始まります。変圧器を通して建物に低圧電力が供給されることを確認し、キュービクル内の表示灯や計器に異常がないかチェック。建物側のブレーカーを順次投入し、各系統へ電気を復旧します。
全設備が正常稼働すれば復電作業完了となります。
かくしてキュービクル切替工事が無事終了し、新設備での電力供給が始まります。
15)PCB検査の実施(PCB検査結果証明書)【電気工事会社】
キュービクルの中にある古い変圧器やコンデンサには、PCB(ポリ塩化ビフェニル)という有害物質を含む絶縁油が使われていた可能性があります。PCBは毒性が強く環境汚染のおそれがあるため、現在使用が禁止されており、含有機器は法定期限までに廃棄処分しなければなりません。そのため、今回撤去した古いキュービクルの変圧器等についてPCB検査を行うことが強く推奨されます。
PCB検査は、専門機関で絶縁油のサンプル分析を行う方法で実施します。撤去した変圧器や進相コンデンサから微量の油を採取し、国が認定した分析機関に提出します。数週間ほどでPCBの有無と濃度が判明します。(詳細はこちらの記事をご覧ください)
もしPCBが含まれていた場合は、施工業者や専門廃棄物処理会社と相談して処理手続きを進めます。処理費用は数十万円ほどと高額ですが、これは法律上避けて通れない責務です。一方、検査の結果PCBが不検出であれば通常の産業廃棄物(金属スクラップ)として処理できます。いずれにせよ、古い設備の更新時はPCBリスクに対処する機会ですので、検査実施をお勧めします。
❹後日対応
16)「電気工事費用+主任技術者の立会い費用」の支払い【お客様】
工事完了後は、契約時の取り決めに従い、所定の期日までに振込などで工事費を支払います。
東京電力への工事負担金は、多くの場合、工事着手前に全額を納めますが、実際の工事が終了した段階で実費と照合し、差額があれば返金または追加請求が行われます。たとえば100万円を預託していた場合、実工事費が95万円であれば5万円の返金、逆に105万円かかった場合は不足分の5万円を追加で支払うという仕組みです。清算結果については後日通知が届きますので、その内容に従って手続きを進めます。
なお、主任技術者への工事立会い費用は、通常の月次・年次点検料に含まれない場合が多いため、事前に確認しておくことが望ましく、必要に応じて別途費用を支払う必要があります。
【まとめ】
以上が、東京電力管内で実施されるキュービクル(高圧受電設備)更新工事の主な流れと、お客様側で取り組むべき事項です。
事前準備から後日の対応まで順を追って見てきましたが、キュービクル更新工事は専門的で関係者も多いため大変そうに感じるかもしれません。しかし、信頼できる電気工事会社と保安担当者のサポートのもと計画的に進めれば、お客様の負担は主に各種意思決定と連絡調整に集中できます。
古い受電設備を放置すると重大事故につながるリスクがあります。「いつかは交換しないと…」と悩んでいる方はぜひ早めに動き出すことをおすすめします。設備更新によって安全性が向上し、テナントや従業員にも安心して電気をご利用いただけるようになるでしょう。今回解説したポイントを参考に、自社の状況に合わせた計画作りにお役立てください。
この記事を書いた人

