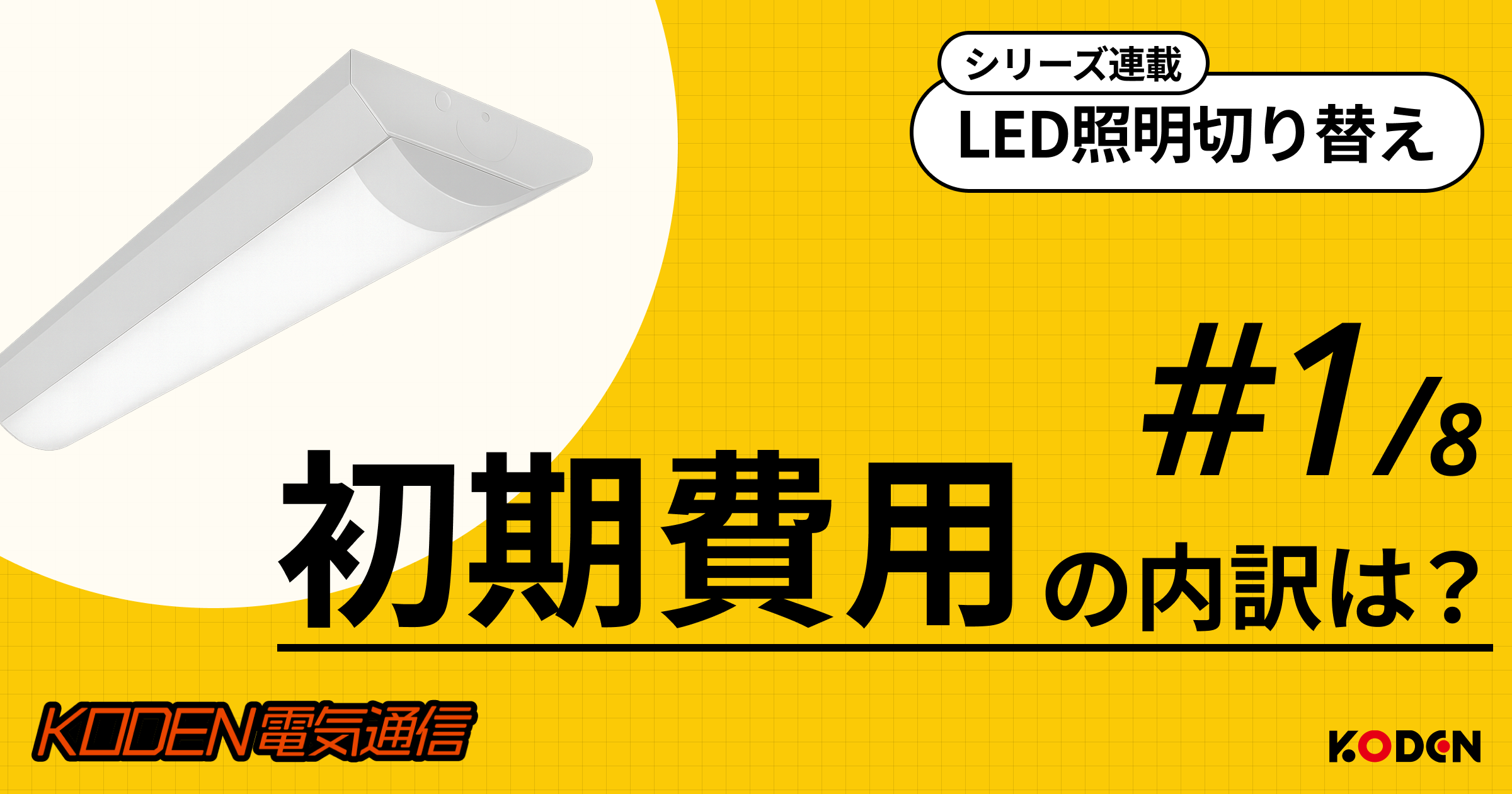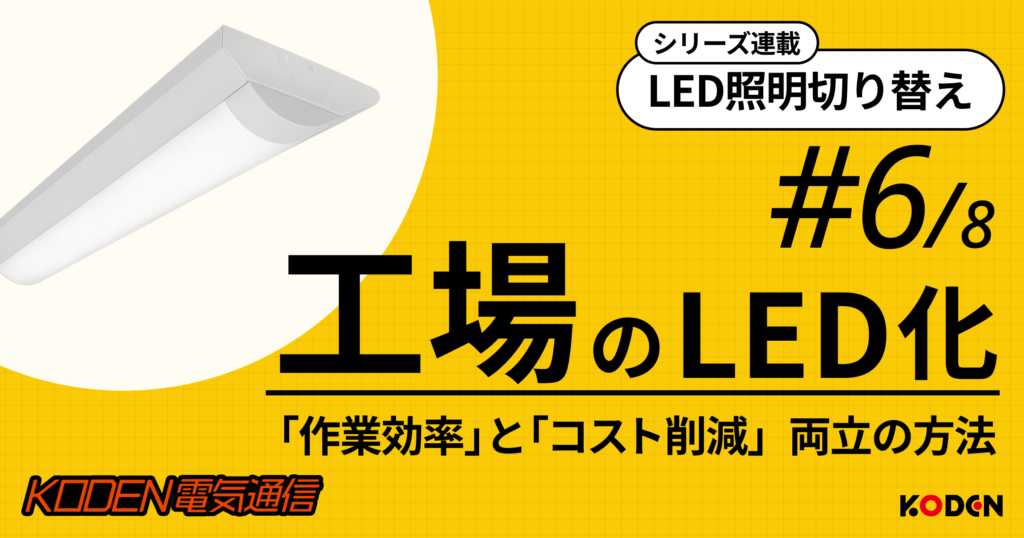【照明(LED)交換工事の手順】結局、お客様(設備オーナー)は何をすれば良いのか?[東京電力管内]
カテゴリー:
タグ:
更新日:2026年2月5日
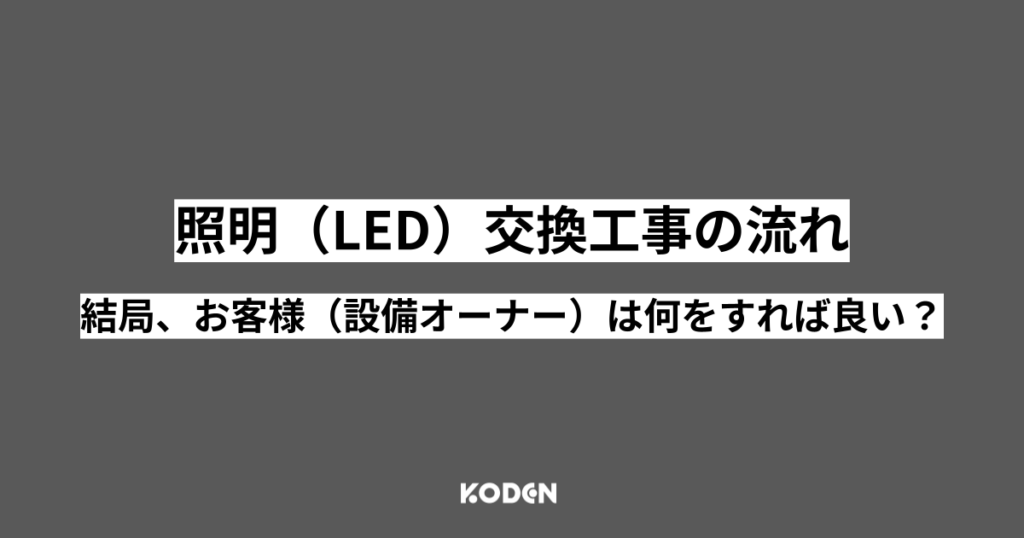
環境負荷を減らし、省エネルギー化を実現するために、蛍光灯からLED照明への交換工事を検討・実施される企業・施設オーナーが増えています。
2027年末には一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が終了することが決まっており、今後は新品の入手が難しくなることが予想されます。現在お使いの蛍光灯を継続利用することは可能ですが、安定した運用のためには計画的なLED更新が不可欠です。
LED照明への更新は、省エネ・明るさ改善・保守負担の軽減などのメリットに直結する一方、施設の規模が大きいほど関係者や工程も増え、各所との調整が複雑になりがちです。
そこで本記事では、「事前手続き」→「 工事当日までの準備」→「工事実施」→「後日対応」の4ステップで、 LED交換工事の全体像とオーナーが実際に行うべきことを分かりやすく整理します。
▼関連記事はこちら
監修

❶事前手続き
1)お問い合わせ・現状資料のご提出【お客様】
まずは電気工事会社へ「蛍光灯をLEDへ交換したい」「見積りを依頼したい」とご相談ください。
打ち合わせと現地確認をスムーズに行うため、分かる範囲で構いませんので、下記のご情報の準備をお願いします。
- 施設の図面
- 既設照明の型番・台数・制御方式:スイッチ位置、人感センサーや調光機能の有無かなど
- 現況写真:器具のアップ写真、空間の全体が見える写真など(養生が必要な領域が分かるものがあると現地確認がスムーズです)
- 交換の目的:省エネ/明るさ改善/眩しさ低減/演色性向上 など
- 現場での作業内容:検品・精密作業・フォークリフト動線など(内容により、照度基準・配光・色温度・防塵防湿等の選定が異なります)
また、このタイミングで、希望工事時期を伝えておくと計画がスムーズに進みます。
2)現地確認の実施【電気工事会社】
お問い合わせ後、電気工事会社が現地を確認します。主なチェック項目は次のとおりです。
- 天井の高さ・搬入経路:高所での作業となる場合、高所作業車の侵入可否や、床耐荷重、通路幅の確認を行います。
- 分電盤・回路:容量、ブレーカー構成、非常回路、誘導灯の交換有無を確認します。
- 器具接続方法について:天井下地、照明器具への配線ルートを確認し、既設配線の再利用の可否などを確認します。
- 既存の器具を活用する場合は「安定器」を外すバイパス工事などが必要です(器具改造等を行うと、器具はメーカー保証の対象外になりますのでご注意ください)。
- 器具自体にも寿命があるため、器具ごと交換を行うことをおすすめします。
- 安全・衛生:アスベストや粉塵などの可燃性物質による火災や爆発の危険性(防爆区域)、食品工場であれば衛生区分等についても確認を行います。
3)注意事項と施工方法の打ち合わせ【お客様+電気工事会社】
現地確認を踏まえ、電気工事会社と施工方法や注意事項の打ち合わせを行います。具体的には下記についてです。
- 稼働への影響最小化:照明交換工事を行う場所の操業時間を確認し、最小限の影響に留まるよう調整します。場合によっては、土日・夜間の工事、部分停電の実施など調整を行います。
- 養生計画:天井での工事となりますので、作業中に発生したゴミから守るために、商品・設備・通路などを養生シートで事前に覆うことで、影響を最小限に抑えることができます。
- 連絡網・責任分担:現場責任者や緊急連絡先などを確認します。また、お客様の立会い範囲もここで確認します。工事当日はお立会いをお願いします。
4)交換灯具の選定・仮仕様書作成【お客様+電気工事会社】
施工に関する注意事項等の内容に合意をいただけましたら、交換灯具の選定に移ります。その際は、下記項目に注意しながら選定を行います。
- 色温度・演色性・グレア:オフィスや倉庫など、環境・用途に合わせて選定します。
- 環境性能:防塵・防水に関する性能を表すIP等級や、防湿、耐塩害、防爆など使用環境に合わせた性能の要否も踏まえて選定します。
- 制御方式:必要に応じて、人感・明るさセンサ、時間や調光パターンの設定などの制御システムをもった灯具を選定します。
- 非常灯・誘導灯の法令適合:非常灯の設置基準は「建築基準法」、誘導灯の設置基準は「消防施行規則」にて定められており、求められる性能も異なります。事前に法令規則を確認しましょう。
▼関連記事はこちら
5)見積書・工事計画書の提出【電気工事会社+お客様】
現地確認や打ち合わせ内容を踏まえて、工事会社は照明交換工事の見積書を作成します。
一般的に見積書提示までは現地確認完了から1〜2週間程度です。見積書には以下の内容が明記されます。
- 工事費用の内訳:器具・施工・高所作業車・夜間/休日割増・養生・廃棄
- 工程概要:工事期間、提出物一覧
- 注意事項:見積り有効期限や支払い条件、施工条件など
また工事が大規模な場合や複雑な場合は、工事計画書を作成し、提出いたします。計画書には、他にも工事の概要、日程、作業手順、安全対策、緊急時対応などが記載されます。
6)ご契約手続き【お客様】
提示された見積りおよび工事内容に納得したら、工事会社との正式な契約を交わします。一般的には見積書にサインをし、工事請負契約書を取り交わします。ここで契約が成立したら、以降は工事会社が主体となって各種手続きや工事準備を進めていきます。
❷工事当日までの準備
7)電灯配置図・器具リストの作成【電気工事会社】
契約締結後、電気工事会社は電灯配置図を作成し、設置場所ごとの照明配置を明確にします。
あわせて器具リストを作成し、使用する照明器具の種類・数量・仕様を一覧化。これにより、材料手配や在庫管理がスムーズになり、施工ミスの防止につながります。
8)工事日程の決定・テナント/現場周知【お客様+電気工事会社】
次に、両者の希望をすり合わせ、工事日程を正式に決定し、施工時間など具体的なスケジュールを確定します。
停電時間は工事内容によりますが、部分停電で完了するよう計画されることが一般的です。工事範囲が大きければ終日停電もあり得ますが、通常は影響を最小限に抑えるため、人員増強や並行作業でできるだけ短時間で復電できるよう工夫します。
❸工事実施
9)最終打ち合わせと養生【お客様+電気工事会社】
いよいよ工事当日です。まず作業開始前に、現地に集まった関係者全員で最終打ち合わせを行います。
- 参加者:オーナー様(設備担当者)、工事施工チーム(作業員)
- 確認事項:工事計画書に基づく当日の作業手順、安全管理、役割分担
特に以下を重点的に確認します:
- 停電範囲の確認
- 作業箇所の安全確認
- 非常時の連絡体制
10)施工前検査(基礎データ採取)【電気工事会社】
- 絶縁抵抗の測定
- 照度のベース計測(必要に応じて)
- 既設設備の不具合(断線・劣化配線・安定器異常など)の確認
不具合が見つかった場合は、是正計画を共有し、本工事に支障が出ないよう事前に対策します。
打ち合わせや検査完了後、作業現場の養生(シート設置・落下防止対策)を完了させてから施工に入ります。
11)既存器具の撤去・廃棄物分別【電気工事会社】
既存の器具を撤去する際には、ランプ・安定器・器具本体を分別して回収します。
注意したい点として、水銀を使用した蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」に該当し、許可を持つ業者に収集運搬・処理を委託する必要があります。
また安定器のコンデンサ等は年代によってはPCB(ポリ塩化ビフェニル)という有害物質を含んでいる可能性があります。PCBは毒性が強く環境汚染のおそれがあるため、法定期限内に適切な処理が義務付けられています。
PCBが含まれていた場合は、施工業者や専門廃棄物処理会社と相談して処理手続きを進めます。処理費用は数十万円ほどと高額ですので、早めに確認を行いましょう。
関連記事を読む
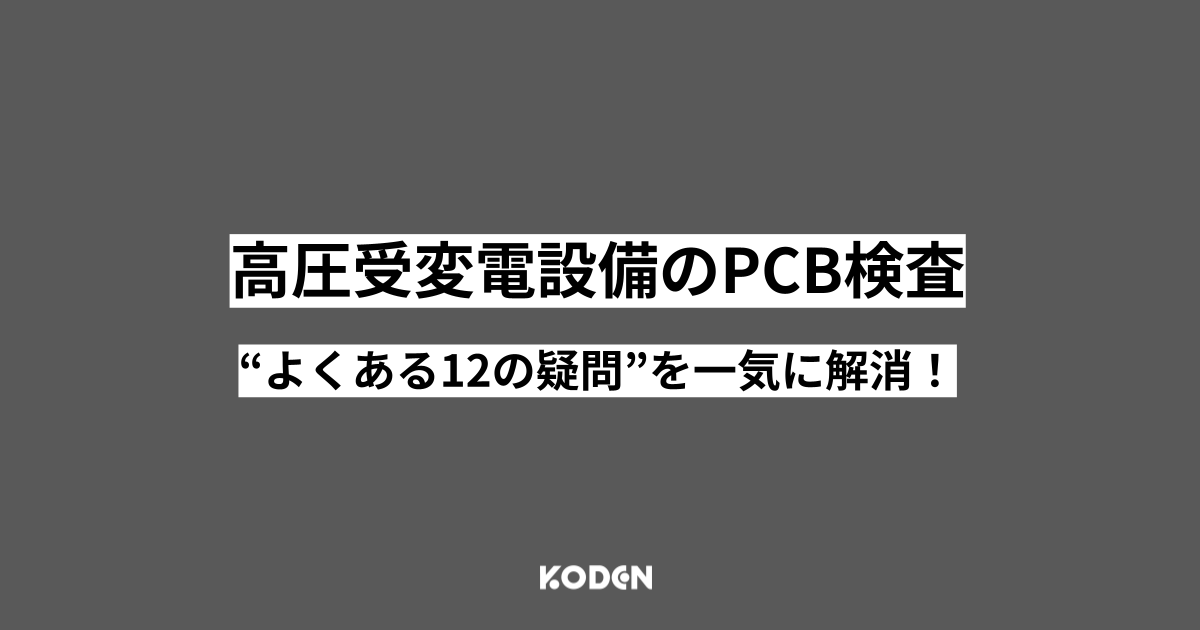
12)新規LED器具の取付・結線【電気工事会社】
新規のLEDを天井下地に固定し、結線作業を行います。固定する際は、締め付け不足による落下や、締め付けすぎによる端子の損傷などを防ぐため、端子が適切な力で締め付けられているかをしっかり管理します。
さらに配線保護も行い、断線やショートのリスクを排除します。
13)点灯試験・施工後検査【電気工事会社】
器具取り付け後は、以下の検査を実施します。
- 絶縁抵抗の再測定
- 照度確認(必要に応じて):作業環境に必要な明るさが確保されているか
- 制御機能の動作確認:調光・人感センサー・タイマー等が正常に動作するか
不具合があれば即時に是正し、正常稼働が確認されるまで調整を行います。
14)清掃・原状回復【電気工事会社】
最後に、工事中に発生した粉塵・切粉を清掃し、養生していた通路の開放、仮設の撤去を行い、LED交換工事は完了です。
❹後日対応
15)測定表・報告書の提出【電気工事会社】
工事完了後は、お客様のご要望に応じて、電気工事会社は報告書一式(完成図書)を提出することも可能です。その場合の内容は以下のとおりです。
- 施工前後の測定値(絶縁抵抗・必要に応じ照度)
- 交換前後の写真
- 器具台帳(器具ごとの管理リスト)
- 回路一覧表
- 改修範囲図
これにより、工事内容が正しく実施されたことを客観的に確認できる資料が残ります。なお、特にご要望がなければ省略される場合もあります。
16)保証書・取扱説明・省エネ効果提示【電気工事会社】
今回の工事で新しく設置したLEDのメーカー保証・施工保証(条件・窓口)が提示されます。
併せて想定削減効果(消費電力・保守費・定格寿命)と運用上の注意点もお伝えしますので、ご確認ください。
17)工事費用の支払い+産廃マニフェスト保管【お客様】
工事会社からの請求書を受領したら、契約で定められた支払条件に従い、期日までに工事費用を支払います。
一般的には月末締め翌月払いや、工事検収後○日以内などの条件が多いです。期日を過ぎないよう社内の経理処理を進めましょう。
水銀を使用した蛍光灯を廃棄した場合は前述のとおり「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬、または処分の許可を受けた専門業者に委託する必要があります。
その際、ご希望であれば産業廃棄物管理票(マニフェスト)を返送してもらうことも可能です。最終処分事業者がすべての処理を完了した際に発行されるこのマニフェストには、5年間の保存義務が定められています。適切な保存をお願いします。
また、必要に応じて運用後の点検スケジュールを設定する場合もございます。
施工事例
まとめ
ここまで、LED交換工事の流れとお客様が取り組むべきポイントを整理してきました。
振り返ると、成功のカギは以下の4点に集約されます。
- 的確な事前情報の提供(図面・写真・目的の共有)
- 現地実態に即した照明器具の選定(照度・配光・環境条件)
- 安全と品質を重視した施工(停電手順・法令遵守・PCB処理)
- 数値と写真による施工報告(測定値・報告書・保証書)
これらを信頼できる電気工事会社とともに進めれば、オーナー様の負担は意思決定と連絡調整に集中でき、スムーズに工事を終えることができます。また「工事不要型のLED器具」を導入する場合でも、既存器具の安定器の状態確認は必須です。
2027年末には一般照明用蛍光灯の製造・輸出入が終了します。終了直前には駆け込み需要が増え、希望する時期に工事ができないリスクも考えられます。
ぜひこの記事を参考に、自社の状況に合わせた計画的なLEDへの交換を進めていただくための計画作りにお役立てください。
この記事を書いた人