【PAS・UAS(UGS)更新工事の手順】結局、お客様(設備オーナー)は何をすれば良いのか?[東京電力管内]
カテゴリー:
タグ:
更新日:2025年12月22日
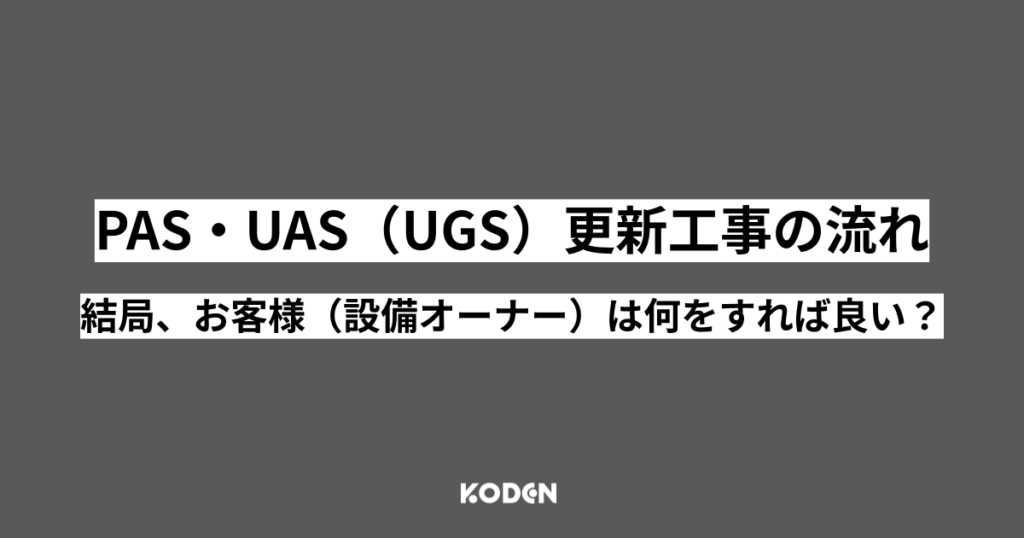
高圧受電設備に設置されるPASやUASは、建物と電力会社の配電網をつなぐ重要な開閉器です。
PASは「Pole Air Switch(ポール・エアー・スイッチ)」の略称で、電柱上に設置される気中負荷開閉器。UASは「Underground Air Switch(アンダーグラウンド・エアー・スイッチ)」の略で地中引込用の気中負荷開閉器を指します。いずれもお客様設備側で異常が発生した際に電気を自動遮断し、周囲への停電被害(波及事故)を防ぐ保護装置です。
現在、事業用受電設備にはほぼ必ずPAS(またはUAS/UGS)が設置されますが、経年劣化したPAS・UASは正常に動作しなくなるリスクがあり、事故防止のため適切な時期での更新が推奨されています。経済産業省の統計でも、PAS普及から30年が経過した近年では老朽化による事故が増加していることが報告されており、官民一体でPASの計画的な更新が呼びかけられています。
メーカーによれば、環境によっては導入後7~10年程度で制御装置の劣化が始まり、正常動作が難しくなるケースもあるため、日常の点検・保守に加え早めの交換検討が大切です。
本記事では、PAS・UASの更新工事について、「事前相談・見積り」「工事準備」「工事実施」「工事完了後」の4つの段階に分けて、具体的な流れとオーナー様が行うべきことを解説します。
監修

❶事前相談・見積り段階
1)お問い合わせ・必要書類の提出【お客様】
まずは電気工事会社(更新工事を請け負う業者)へ「設備を交換したい」「見積りを依頼したい」と相談します。この初期問い合わせの際に、オーナー様側でご準備いただきたい主な書類・情報は以下のとおりです。
- 設備の点検記録(定期点検報告書):外部の保安協会や選任している電気主任技術者から交付された月次・年次点検報告書があれば用意します。過去の指摘事項や不具合履歴が分かると、新しい機器を選定する際に役立ちます。
- 受電設備の図面類:現在使用している受電設備の単線結線図や系統図、構内配置図です。委託している主任技術者が用意できるケースが多いため、不明点があれば主任技術者にも確認しましょう。
問い合わせを受けた工事会社は、交換工事に必要となる書類の提出を依頼するとともに、工事の大まかな流れや概算の費用感、スケジュール感について頭出し(大まかな説明)を行います。
オーナー様としては、上記書類を準備しつつ、希望する工事時期や現在の設備で気になっている点(例えば老朽化の程度や不具合症状)などを伝えておくとスムーズです。
2)現地確認の実施【電気工事会社】
工事会社の担当者が実際の設置場所や既存設備の現地確認を行います。
担当者(場合によっては施工管理技士や現場監督級のスタッフ)がオーナー様立会いのもと設備の状態を詳しく確認し、交換工事の可否や詳細な要件、必要な機材・資材を洗い出します。現地確認で主にチェックされるポイントは以下のとおりです。
- 設置場所と作業条件の確認:PASが設置されている電柱やUAS収容箱の場所を確認し、交換作業の方法を検討します。高所にあるPASなら高所作業車の設置スペースや道路幅、周囲の障害物(樹木・看板等)をチェックします。UASの場合は高圧キャビネットの位置や作業スペース、重機搬入経路などを確認します。必要に応じて道路使用許可が要るかどうかもこの時点で判断します。
- 既存設備の劣化状態:交換対象のPAS・UAS本体や付属品(避雷器LAや電圧計VT付きか否か等)の現状を確認します。腐食や破損がないか、適切に機能しているかを点検します。また周囲の高圧引込ケーブルや支持金物、基礎(架台)の状態も確認し、追加で交換・補修すべき箇所がないか洗い出します。
- 必要機器と工法の検討:新たに設置するPAS・UASの仕様を検討します。現在は、方向性(敷地外での事故により不要に動作することを防ぐ)を有した機器が一般的に使用されています。
周辺環境によっては重耐塩形(塩害対策品)を選定するなど、最適な機種を検討します。あわせて、交換作業に必要な人数や重機も検討します(電柱工事の場合、電力会社側と自社双方で高所作業車が必要になるケースが一般的です)。
※なお、恒電社では現地確認にかかる費用は無料で対応しています。
確認の結果、新たな課題や追加工事項目が判明した場合でも、この段階でしっかり洗い出しておくことで後々のトラブル防止につながります。
3)正式見積書・工事計画書の提出【電気工事会社】
現地確認で得られた情報をもとに、工事会社は交換工事の見積書を作成します。一般的に見積書提示までは調査完了から1~2週間程度です。見積書には以下の内容が明記されます。
- 工事名称・工事範囲:例:「PAS更新工事(高圧引込ヒューズホルダ含む交換)」等、今回の交換対象となる機器や範囲が記載されます。
- 工事費用の内訳:PAS・UAS本体の機器代、工事施工費(人件費・重機費用等)、付帯工事費(古い機器の撤去処分費など)が細かく内訳として示されます。特殊条件による割増費用(夜間施工や狭所作業など)があれば項目に含まれます。
- 工事期間:実際の停電作業は半日程度でも、事前準備や後片付けを含め○月○日から○月○日まで、といった日程が記載されます。通常、停電作業日は1日と想定されますが、天候等で順延する場合の予備日設定について触れられる場合もあります。
- 適用条件:見積り有効期限や支払い条件(例:工事完了後○か月以内に銀行振込)、注意事項などが添えられます。
オーナー様は提示された見積書の工事範囲と金額を十分に確認しましょう。不明な費用項目があれば施工業者に質問し、納得したうえで次の意思決定に進みます。
場合によっては工事内容の調整(例えば「今回はPASだけでなく老朽化した避雷器も交換したほうがよいのか?」等)について業者からアドバイスを受けることもあります。そうした点も踏まえて検討し、社内稟議や予算取りを進めます。
また、恒電社ではこのタイミングで工事計画書を作成し、送付しています。ご希望の時間帯をヒアリングした上でスケジュール表を作成しますが、受注前(電力申請前)のため、未確定の段階です。計画書には、他にも工事の概要、日程、作業手順、安全対策、緊急時対応などが記載されます。
4)契約手続き【お客様+電気工事会社】
提示された見積りおよび工事内容に納得したら、工事会社との正式な契約を交わします。一般的には見積書に発注サインをし、工事請負契約書を取り交わす形です。ここで契約が成立したら、以降は工事会社が主体となって電力会社との各種手続きや工事準備を進めていきます。
契約にあたり、もし費用面で調整が必要な場合はこの時点までに行います。たとえば複数社から相見積りを取得している場合、金額やサービス内容を比較し信頼できる業者を選定します。また契約に際しては、以下の書類をご提出いただきます。
- 直近の「電気料金明細書」:契約中の電力会社のお客様番号や契約電力が記載されています。
高圧設備工事は専門性が高いため、価格だけでなく実績や対応力を考慮して発注先を決めることが重要です。なお、設備オーナーがビル管理会社や設備管理会社を経由せず直接専門の電気工事会社に発注することで中間マージンを省きコストダウンになるケースもあります。可能であれば直接契約が望ましいでしょう。
最後に、契約書には工事内容や金額のほか工事予定時期も明記されます(過去の事例より土日祝日の工事を希望される場合は工事可能となるまで時間が掛かりますので早めに決定いただくことをお勧めします)。
ここで決めた大まかな工事時期をベースに、次の段階で電力会社との具体的な日程調整へと進みます。
❷ 工事当日までの準備・申請
5)電力会社への工事申請【電気工事会社】
契約締結後、工事会社は東京電力に対してPAS・UAS交換工事の申請を正式に行います。高圧受電設備の主要機器を交換する場合、管轄の電力会社への申請・工事依頼が必須です。
通常、この手続きは工事会社がオーナー様に代わって代理申請します。例えば東京電力管内では「工事申込書」を提出し、内容審査後に受付が完了します。申請時に電力会社へ提出される資料の例は以下のとおりです。
- 工事申込書(所定様式):電力会社所定のフォーマットに、工事内容や停電の必要性、希望日程等を記載した申込書です。
- 受電設備の単線結線図:更新後の新しいPAS・UASを反映した高圧受電設備の結線図面を提出します。
- 構内配置図:PASや高圧引込の位置関係が分かる見取図を添付します。屋外のPASなら電柱の位置、UASなら高圧キャビネットの場所が示されます。
- 現地写真:設備周辺の状況が分かる写真も求められる場合があります。作業条件や周囲環境を事前に電力会社が把握するためです。
電力会社は提出された資料をもとに工事計画を策定します。内容に問題がなければ申請が受理され、以降は電力会社と調整しながら工事を進めることになります(万一申請内容に不備や問題点があれば工事会社経由で連絡・協議が入ります)。
6)工事日程の調整・確定【お客様+電気工事会社+主任技術者】
電力会社への申請後、実際に工事(停電作業)を行う日程の調整に入ります。高圧設備の停止・送電復旧には電力会社の立ち合いと作業が必要となるため、電力会社側の都合も考慮して日程を決める必要があります。流れとしては以下のようになります。
- オーナー様および電気主任技術者から希望日の聴取:まず工事会社がオーナー様に対し、「○月下旬~○月中旬で都合の良い日」「停電して支障の少ない時間帯」などの希望を複数挙げてもらいます。同時に、設備の保安担当である主任技術者(自家用電気主任技術者)にも立会い可能な日程を確認します。ビル利用者に影響が出にくい夜間・休日を希望するケースも多いです。
- 電力会社へ候補日の提示:工事会社は取りまとめた複数の希望日程候補を電力会社に提示します。「第1希望○月△日、第2希望…」という形で伝え、電力会社側の工事可能日を打診します。
- 電力会社から工事可能日の提示:電力会社は自社の配電線工事スケジュールや要員手配状況を踏まえ、「この中なら○日と○日なら対応可能」という形で回答をくれます。場合によっては希望日が全て埋まっており別日提案となることもあります。
- 最終日程の確定:電力会社から提示された候補日の中から、オーナー様・工事会社・主任技術者の三者で最終的な工事日を決定します。全員が立ち会える日時であること、停電による業務影響を最小化できる日時を考慮して調整します。一度決まった工事日は極力変更できないため、社内調整(テナントや従業員への周知など)も念頭に置きながら慎重に決めます。
※PAS・UAS更新工事は関係者が多く日程調整が大変ですが、できるだけ早期から計画を進めておくことが望ましいです。専門家は「危険性と費用を伴うPAS交換は1~2年前には日程を決定しておくべき」と助言しています。特に施設の稼働を止められる日が限られる場合や、年度切替に合わせたい場合など、余裕をもってスケジュール調整を開始しましょう。
7)機器・資材の手配【電気工事会社】
工事日が確定したら、それに向けて必要機材の手配を進めます。交換用の新しいPAS・UAS本体はもちろん、付帯部材(例えば高圧ケーブル端末処理キット、支持金具、ボルトナット類、必要に応じてその他の機器を工事会社が発注・準備します。
製品によっては納期が数週間~数か月かかるため、日程に遅れが出ないよう早めに発注します。特注仕様や在庫稀少品の場合、工事日までに届くよう注意深くスケジュール管理されます。
また工事に使用する重機・工具類の準備も行います。例えば電柱上のPAS交換では、高所作業車やクレーン車を使用します。道路幅や現地条件に合った車両を手配し、必要なら事前に搬入経路の下見も行います。
停電時間を短縮するため、事前に可能な準備作業(仮配線や機器の組立等)は工事前日までに済ませておくよう工程を組みます。こうした入念な準備により、当日の作業をスムーズに進めることができます。
8)各種許可申請の提出【電気工事会社】
必要に応じて行政への許可申請も行います。例えば工事現場が公道に面しており、高所作業車の路上駐車や道路占用が避けられない場合、所轄警察署に「道路使用許可」や「道路占用許可」を事前に申請します。クレーンを使用して道路上空で機器の吊り上げ作業を行う場合も同様です。申請手続きは工事会社が代行しますが、オーナー様には道路使用料などの実費負担が発生するケースもあります。
その他、鉄道や高度な安全管理が求められる施設の場合は事前にリスクアセスメントを行い、計画書に反映します。関係各所への届け出(消防署やビル管理会社への作業通知など)が必要な場合も、この段階で漏れなく済ませておきます。
9)周辺テナント・近隣への周知【お客様】
工事当日に停電や作業音が発生する場合、事前に周囲への周知と協力依頼を行うことも重要です。特にビルや工場の場合、同じ建物のテナント企業や施設利用者に対し停電予定の日時を通知し、理解を得る必要があります。オーナー様(またはビル管理会社)は「停電のお知らせ」文書を作成し、配布・掲示しましょう。通知内容には停電時間帯や工事内容、問い合わせ先などを明記します。
停電に伴い各テナントに協力してもらいたい事項も事前に伝えます。例えば「○時までにPCやサーバをシャットダウンしてください」「エレベーター停止位置を調整します」「冷蔵設備の保護のため開閉を控えてください」などです。
また、近隣住民にも騒音や作業車両の出入りについて必要に応じ周知しておきます。長時間の停電となる場合は、非常用電源の準備や仮設発電機の手配も検討が必要です(工事会社と相談しましょう)。
以上が工事前日までの準備段階です。しっかりと計画・準備を行うことで、いよいよ次は工事当日の実施に臨みます。
❸ 工事当日の作業
10)関係者による最終打ち合わせ【お客様+電気工事会社+主任技術者+電力会社】
いよいよ工事当日です。まず作業開始前に、現地に集まった関係者全員で最終打ち合わせを行います。オーナー様(設備担当者)、工事施工チーム(電気工事会社の作業員)、選任の主任技術者、電力会社作業員が顔合わせし、当日の作業手順や安全管理、各自の役割分担を再確認します。
この場では、工事計画書に沿って当日の流れを復唱し、特に安全確保について念入りに確認します。高圧設備の停電手順(どの順序で開閉器を操作するか)、作業箇所の指差呼称、非常時の連絡系統などを打ち合わせます。いわゆる「朝礼」「安全ミーティング」にあたるもので、工事会社の責任者が進行し、主任技術者や電力会社から注意事項の共有があればここで周知されます。
必要な書類の確認も行います。例えば作業員の資格証携行チェック、使用工具・保護具の点検、高所作業車の点検、工事許可証の現場備え付け確認などです。全員が準備万端整ったことを確認したら、いよいよ停電作業に移ります。
11)高圧受電設備の停電措置【電力会社+主任技術者】
まず電力会社の担当者により、建物に電気を送っている高圧配電線からの送電を停止してもらいます。具体的には、電柱上の引込線に設置された電力会社側の開閉器(電力会社設備のAS)を開放(オフ)し、建物側への高圧送電を遮断します。これによってPAS・UASなど高圧受電設備は無電圧状態となり、工事作業を安全に行える状態になります。
加えて、建物内の高圧受電設備側でも必要な遮断操作を行います。通常、自家用受電設備には高圧受電用の遮断器(断路器やVCBなど)があり、主任技術者の立ち会いのもとで停電操作を実施します。電力会社が引込側を遮断し、主任技術者が受電設備側を遮断することで、作業対象区間を完全に電源から切り離します。
- 停電の確認:遮断操作後、作業員は検電器を用いて対象設備に電気が来ていないことを確認します。「活線作業厳禁」が鉄則のため、高圧ケーブルや機器に残留電荷がないか必ずチェックします。全ての相で無電圧を確認したら、作業許可がおり交換作業に入ります。
※弊社では安全のため、主任技術者による停電作業に担当者が必ず同席し、停電が確実に行われていることを目視確認します。
12)既設PAS・UASの撤去【電気工事会社】
まず、古いPAS・UAS(交換対象機器)の取り外し作業を行います。停電が確実に確認されたら、撤去手順に従って作業開始です。
- 高圧引込線の分離:PASの場合、電柱上で配電線(電力側引込線)とPAS本体を接続しているリード線を外します。UASの場合は高圧キャビネット内でケーブル接続を開放します。
- 設備本体の取り外し:PASならポール上で機器固定金具を外し、クレーンや高所作業車で慎重に吊り下ろします。重量物のため落下させないよう注意しながら地上へ降ろします。UASの場合はキャビネット内での固定を解き、機器を取り外して撤去します。
- 古い機器の搬出・処分:取り外した既設PAS・UASは廃材として回収し、工事会社がトラックで搬出します。変圧器のようなPCB含有油はありませんが、念のため機器内部の状態を確認し適切に産業廃棄物として処理します。
撤去作業では安全かつ迅速な手順が求められます。例えばPAS撤去の一般的な手順は、電力側接続解除 → 負荷側接続解除 → 接地線解除 → 機器固定解除 → クレーン吊り下ろし…という流れで行われます。熟練の作業員が連携すると、約1~2時間程度で撤去は完了します。
13)新PAS・UASの据付・結線【電気工事会社】
続いて新しいPAS・UASの設置を行います。基本的には先ほどの撤去手順の逆の順序で進めます。
- 新機器の搬入:事前に現地まで運んでおいた新品のPAS・UASを作業箇所へ移動します。PASならクレーンや高所作業車で電柱上部まで吊り上げ、所定の位置に据え付けます。UASならキャビネット内に慎重に機器を設置します。機器の耐圧試験は撤去作業中に並行して行っておきます。
- 固定・据付:PASは取り付け金具で柱上の腕金に確実に固定し、振動で緩まないよう増し締めも行います。UASもキャビネット内レール等に確実に固定します。
- 高圧ケーブルの接続:負荷(受電設備)側リードを既設ケーブル端末端子に接続します。UASの場合も同様にケーブル端末を新機器の端子台に確実に接続します。接続後、増し締めと目視点検を行い、導通箇所の緩みや異常がないことを確認します。
- 付属機器の接続:PAS・UASに付属する制御線や接地線も忘れずに結線します。SOG制御器のリレー試験もここで実施します。
- 電源側リードの接続:電力会社側からの高圧引込線にも新PASの電源側リード接続します。
新設置が完了したら、見た目上は新品のPAS・UASが所定の位置に収まり、接続も完了した状態になります。ここまでの工程もおおむね1~2時間程度です。
14)試験・点検の実施【電気工事会社+主任技術者】
据付・結線が終わったら、送電復旧の前に各種試験と点検を行います。新しい機器が正常に動作するか、安全に使用できる状態か確認する重要なステップです。
- 外観点検:まず機器の外観や取付状態をチェックします。ボルトの締め忘れがないか、端子カバーが正しく装着されているか、異常な傷や汚れがないか確認します。
- 絶縁抵抗測定:高圧回路の絶縁抵抗値を絶縁抵抗計(メガー)で測定し、十分な絶縁が保たれていることを確認します。交換したPAS・UASの各相-接地間で所定の絶縁抵抗値以上あることが求められます。
- 耐圧試験:必要に応じて、高圧回路に試験電圧をかける耐圧試験を実施します。新設機器や接続部が高電圧に耐えられるか検証し、不良箇所がないことを確認します。試験後は再度絶縁抵抗も測定します。
- 動作試験(開閉動作の確認):PASであれば開閉動作を試し、スムーズに開閉できるか確認します。遠隔トリップ機能や継電器付きの場合は、テストボタンを押すなどして遮断動作を確認します。UASも同様に投入・開放操作を試験し、問題ないことをチェックします。
これらの試験は、主任技術者または指示のもとで工事会社が実施します。主任技術者は「使用前自主検査」として機器の試験結果を確認し、設備が技術基準に適合していることを確認します(法令上、高圧設備の重要な変更時には主任技術者による使用前検査が義務付けられています)。全てのチェック項目をクリアしたら、いよいよ送電となります。
15)送電復帰(復電)作業【電力会社】
電力会社の担当者により、停止していた高圧送電を再開します。具体的には、工事前に開放していた電柱上の開閉器(電力会社のAS)を再投入(クローズ)し、建物への電気供給を復活させます。これにより、新しいPAS・UASに電気が通電され、建物内の受電設備まで再び高圧電力が供給されます。
送電再開にあたっては、まず工事会社・主任技術者から電力会社へ「復電準備完了」の連絡を入れます。電力会社作業員が安全を確認した上で所定の手順に従い開閉器を操作し、送電開始します。復電時にはPASが解放された状態になっていることを事前に確認しておきます。その後主任技術者により安全を確認しながら順次復電操作を進めます。
なお、万一復電直後に異常が発生した場合は、直ちに電力会社が送電を停止できるよう待機しています。
16)最終確認と設備引き渡し【主任技術者+電気工事会社】
通電後、新しいPAS・UASが正常に機能しているか最終確認を行います。主任技術者と工事会社担当者が協力し、以下の点をチェックします。
- 設備の健全性確認:復電後の電圧計や表示灯の状態を確認し、正常に受電できていることを見ます。PAS・UAS本体から異音や異臭がしないか、発熱や放電痕がないか外観を再確認します。
- 動作確認(再):必要に応じて、実際にPASを一度開放→投入操作してみて、負荷への送電が遮断・再開できることを試します(もちろん電力会社と連携しながら慎重に行います)。試験ボタンによってトリップ機能も再チェックします。
最終的に主任技術者が「新しい設備は安全・正常に稼働可能」と判断すれば、全工程完了となります。工事会社はオーナー様に対し、工事が無事完了したことを報告し、新設機器の鍵や取扱説明書、試験成績書などを引き渡します。オーナー様にも目視で新しいPAS・UASを確認していただき、今後の保守点検について簡単な説明を受けます。
こうしてPAS・UASの更新工事は完了です。実際の停電時間は数時間程度で済むことがほとんどで、例えばUAS(地中開閉器)の単体交換であれば停電準備含めおおよそ3時間程度の作業で完了します。現場状況によりますが、熟練した施工チームで計画通り進めば、半日以内に復電まで漕ぎつけることも可能です。
❹ 工事完了後の対応
17)工事費用+主任技術者への立会い費用のお支払い【お客様】
工事完了後、工事会社から請求書が発行されますので、契約時に取り決めた支払い期日までに工事費用を支払います。一般的には工事検収後○週間以内や月末締め翌月払いなどの条件が多いです。期日を過ぎないよう社内の経理処理を進めましょう。
なお、見積書の金額から追加費用が発生した場合(追加工事や不測事態への対応費用など)は、事前の合意に基づき清算されます。今回のPAS・UAS更新工事では追加費用なく予定内で収まるケースが大半ですが、念のため請求内容を確認し、不明点があれば工事会社に問い合わせます。
また、主任技術者への工事立会い費用は、通常の月次・年次点検料に含まれない場合が多いため、事前に確認しておくことが望ましく、必要に応じて別途費用を支払う必要があります。
まとめ
以上が、PAS・UAS更新工事の一連の流れです。事前の打ち合わせから始まり、現地確認、見積り、契約、そして電力会社との調整を経て工事当日・完了後の対応まで、順を追ってご説明しました。
初めて経験されるオーナー様には関係者も多く煩雑に感じられるかもしれませんが、信頼できる電気工事会社と主任技術者のサポートのもと計画的に進めれば、オーナー様のご負担は主に各種意思決定と連絡調整に集中できます。
古い高圧受電設備を放置すると重大事故につながるリスクがあります。もし「いつかは交換しないと…」と不安に感じている方は、ぜひ早めに動き出すことをおすすめします。
適切な時期にPAS・UASを更新することで、設備の信頼性と安全性が向上し、周囲への停電リスクも低減できます。まずは専門業者に相談し、現状の点検や更新時期の目安についてアドバイスを受けてみましょう。
計画的な設備更新によって安心・安全な電力利用環境を維持することが、法人オーナー様にとって大切な責務と言えるでしょう。各種手続きや調整も含め、経験豊富な工事会社に任せればスムーズに進みます。ぜひ早めのご検討で、皆様の事業継続に万全を期してください。
最後までお読みいただきありがとうございました。当社恒電社では高圧受電設備の更新工事について豊富な実績がございますので、疑問点や相談がありましたらお気軽にお問い合わせください。設備の安全・安心な運用を全力でサポートいたします。
この記事を書いた人

