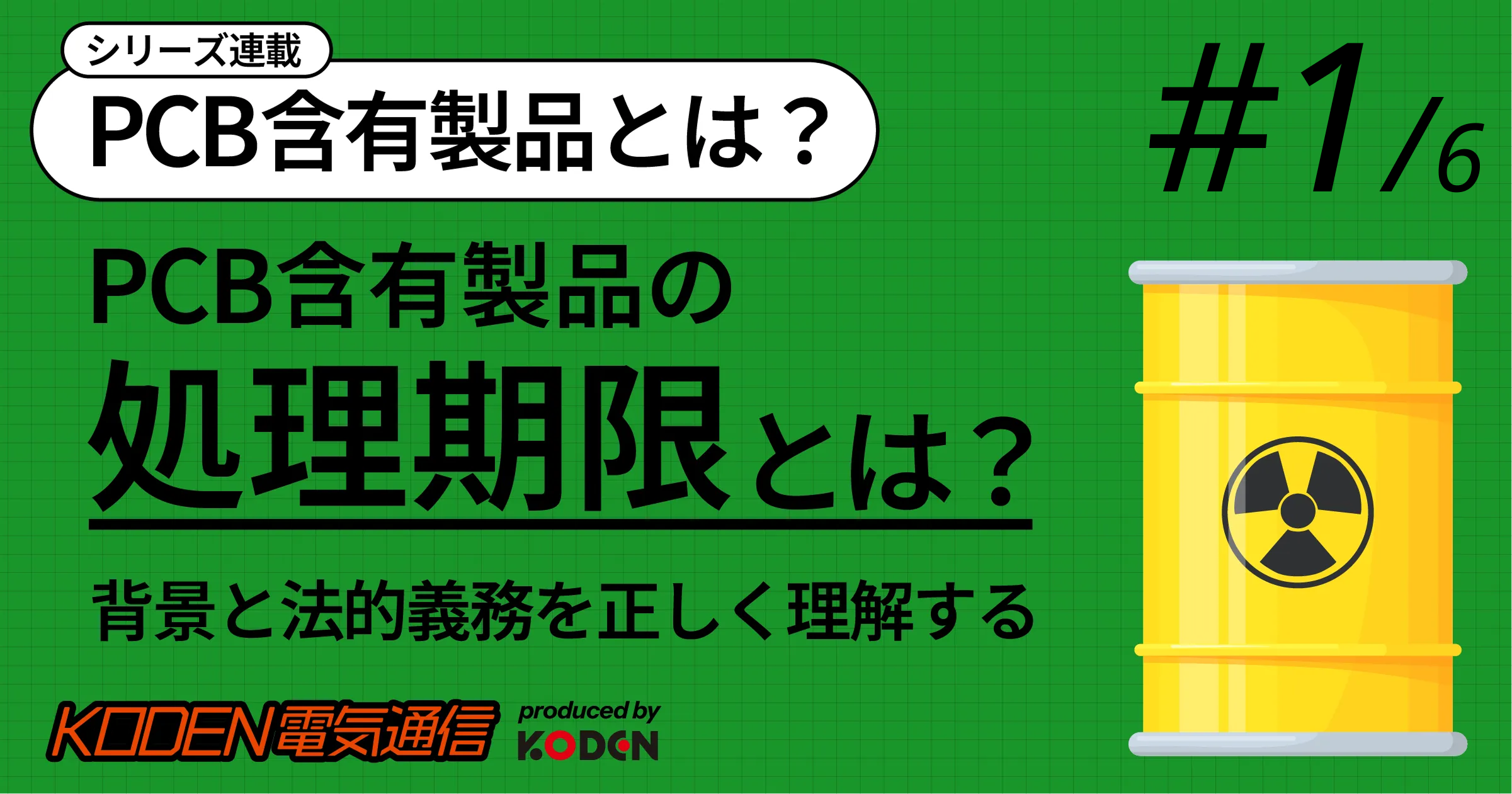【高圧・低圧切替工事の手順】結局、お客様(設備オーナー)は何をすれば良いのか?[東京電力管内]
カテゴリー:
タグ:
更新日:2026年2月5日
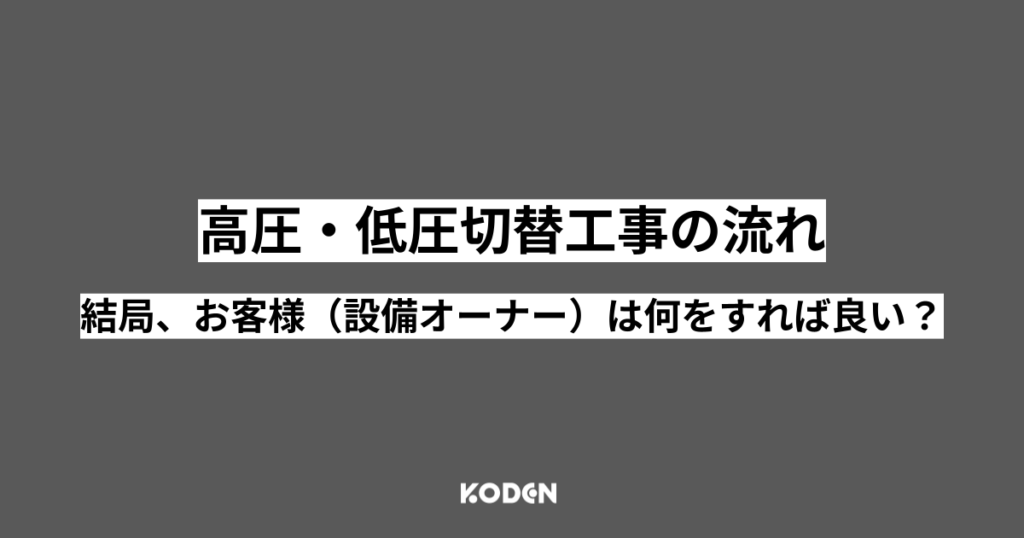
高圧受電設備を低圧へ切り替えると、キュービクル維持費や主任技術者委託料を削減できる一方、東京電力工事負担金の発生や、工事の際の停電作業が必要となります。また、高圧は電気単価が低圧より安い為、低圧化した際に電気代が上がる場合もございます。
本記事では、「❶事前手続き」→「❷工事当日までの準備」→「❸工事実施」→「❹後日対応」の4ステップで、高圧・低圧切替工事の全体像とオーナーが何をすべきかを分かりやすく解説します。
※高圧から低圧へ切り替える工事についてまとめています。低圧から高圧への切り替えに関しては、「キュービクル新設」の記事(近日公開予定)をご確認ください。
▼関連記事はこちら
監修

❶事前手続き
1)お問い合わせ・必要書類のご提出【お客様】
まずは、電気工事会社へ工事の「相談・問い合わせ」を行います。その際、以下の情報をメールや電話でご提出いただきます。
- 月次、年次点検表
- 電力会社からの請求書
- キュービクル単線結線図
併せて「低圧へ切替える目的(コスト低減・設備老朽化など)」を共有いただくと、後工程がスムーズです。電気工事会社はメリット・デメリットを整理し、必要に応じて社内稟議資料のたたき台を用意します。
2)現地確認の実施【恒電社+お客様】
工事担当者が現地を訪問し、キュービクル内部や引込線ルート、分電盤のスペースを実測します。
ボイラー・空調など大負荷機器の仕様を確認し、低圧(100-200V/単相三線・200V/三相三線)での使用可否を判断します。建物用途上の停電許容時間やクレーン車進入経路もここで確認し、後の工程を逆算します。
3)正式お見積りの提出【電気工事会社】
現地確認の結果をうけて、低圧化に伴う工事範囲・概算費用・概算工期を策定します。また、機器の仕様・作業項目・人工を試算。分電盤増設数、幹線ケーブルサイズ、キュービクル撤去搬出費など詳細内訳を提示します。
費用対コスト削減額の概算比較も行い、先行費用回収のイメージをつかむことが重要です。正式見積りが契約金額となるため、社内決裁フローに合わせた分割請求やリース活用の要否も確認しましょう。
4)電力会社との事前協議・工事負担金概算共有【電気工事会社】
正式見積りにご承諾いただけましたら、電力会社との事前協議を開始します。東京電力パワーグリッドと低圧化の可否・受電方法や契約容量を協議し、配電線容量や柱上変圧器(PAS)増設の要否を確認します。
この段階で「工事負担金」(電力会社が電柱や配電線等の供給設備を整備するために必要な費用で、お客様にご負担いただくもの)の概算(架空:30〜50万円/地中埋設:100万円超のケースあり)が提示されます。
お客様へは早期に金額イメージを共有し、予算取りを進めていただきます。
5)注文書・注文請書の取り交わし【お客様+電気工事会社】
概算負担金を含めた総事業費を確定後、電気工事会社とお客様との間で工事請負契約を正式に締結します(契約書取り交わし)。契約書には 支払条件、工期、停電予定時間、瑕疵(かし)担保期間 などを明記します。
地中埋設で負担金が高額になる場合、年度跨ぎ分割や設備投資補助金制度の活用も検討可能です。
❷工事当日までの準備
6)工事申込書(廃止届+低圧新設届)の提出【電気工事会社】
工事契約の締結後に、高圧受電契約の廃止届および低圧受電の新設申込を電力会社に提出し、正式に契約変更プロセスを開始します。
これは高圧契約をやめて低圧に切り替える正式な申請手続きであり、高圧送電を停止する希望日(切替工事の日程)や契約変更の理由などを記載します。申請が受理されれば電力会社内でも準備が進み始め、いよいよ低圧化工事の実施段階へ移行します。
7)主任技術者の解任通知提出【お客様】
高圧受電設備を管理していた電気主任技術者についての手続きも忘れず行います。高圧設備を持つ事業用電気工作物では選任が義務付けられていた主任技術者も、低圧へ切り替えて高圧設備が無くなれば選任義務が消滅します。
外部委託の場合は契約解除交渉、社内有資格者の場合は任命解除を行い、保安監督部(経産省管轄)へ解任届を提出します。通知は工事完了予定日の30日前までに行うのが目安です。もし電気保安協会などと契約している場合は、事前に点検業務停止の相談をし、契約解除の予告期間(例えば3か月前通知など)についても確認しておきましょう。
円滑に低圧移行するため、主任技術者には切替工事の日程や高圧設備の廃止予定日を共有し、必要な立ち会いや作業調整を依頼します。
8)配電線設備の設計・工事負担金確定とお支払い【電力会社】
一方、電力会社側ではお客様からの申請を受け、配電設備の設計および工事負担金の算出を進めます。
建物負荷に応じた引込線サイズ、柱上変圧器容量を設計し、その工事に必要な費用を積算します。こうして確定した工事費負担金の金額が電力会社から正式に通知され、あわせて請求書が発行されます。
お客様は指定された期日までにこの工事負担金を電力会社へお支払いください。負担金の支払いが完了しないと、電力会社は供給設備工事に着手できませんので注意が必要です。
この際、容量増設が不要なら負担金は抑えられますが、電柱新設や地中化要件があると大幅増額の可能性もあります。確定通知書で金額・納期を確認しましょう。
9)低圧電力供給日の確定【電力会社】
入金確認後、電力会社から「低圧送電(受電)開始可能日」が通知されます。
これは電力会社側の設備増強工事が完了または完了見込みとなり、お客様の拠点へ低圧で電気を送れる状態になる日付です。その日付を基準に、実際の切替工事日程(送電開始日)を最終決定します。
❸工事実施
10)低圧用現場配線工事(1回目)【電気工事会社】
電力会社から低圧の送電開始可能日が示されたら、その日までに建物側の低圧受電設備の工事を完了させる必要があります。遅くとも低圧受電開始予定日の1週間前までに、電気工事会社の担当者が建物内で必要な機器設置・改修工事を行います。
具体的には、新たな低圧幹線や分電盤の設置、電力量計(メーター)の取付台の準備、屋内配線の切替え工事や開閉器類の交換などです。
既存の高圧受電設備から各テナント・各階へ電気を供給していた場合は、その配線系統を低圧用に付け替え、テナント毎に個別の低圧契約メーターを設置する工事も伴います(建物の契約形態によります)。
なお、これら屋内配線工事を行う際には一部で短時間の停電が発生する可能性がありますが、停電時間が最短となる様、工法やタイミングを考慮し、テナントへの影響を最小限に配慮して進めます。
11)低圧供給開始【電力会社】
こうした建物側の準備工事が完了した後、電力会社による低圧用メーターの設置および引込幹線接続や通電試験が行われ、建物の低圧契約(低圧電力/低圧電灯)の準備が完了となります。
その上で予定した受電開始日(送電日)になると、電力会社が建物への低圧送電を開始します。高圧契約時と比べ、電気の受け方は変わりましたが、照明やコンセント等への電力供給は問題なく継続されます。
晴れてこの時点から建物内の設備は電柱上の変圧器から供給される低圧電気で稼働できるようになり、低圧料金体系が適用されます。
12)低圧使用への切替え工事(2回目)【電気工事会社】
低圧での受電開始に至るプロセスで、一時的に高圧契約と低圧契約が併存する期間が生じる場合があります。つまり、短期間ではありますが同じ建物に対し高圧と低圧が同時に受電されている状態です。ただし高圧はキュービクルにて電気の供給をとめていますので、お使いいただいているのは低圧電気となっております。
しかしご安心ください。この重複期間はスケジュール上やむを得ず発生させるもので、高圧側を生かしたまま負荷を低圧系統へ順次移し変えます。
契約重複期間中は高圧・低圧両方の基本料金等が日割りで発生しますが、ごく短期間であり実質的な余分コストは最小限です。また、高圧契約の廃止申込書は既に完了しておりますので、この重複期間が終われば正式に高圧契約は消滅し、以降は低圧契約分の料金だけをご負担いただく形になります。
13)高圧受電廃止日の確定【電力会社】
低圧への切替えが完了した後、高圧受電停止日を電力会社が正式決定し、高圧受電設備の廃止工事を行います。これは電力会社および電気工事会社にとって最終段階の大仕事です。
事前に提出していた高圧受電の廃止届をもとに、電力会社との協議で高圧送電を停止する日(=高圧設備を撤去する日)が正式に決定されます。通常、低圧受電開始日からあまり間を空けずに、高圧設備の停止・撤去日程を設定します。
14)高圧受電停止・高圧部材撤去(3回目)【電気工事会社】
廃止日当日、まず電力会社が高圧側の送電を完全に遮断します。具体的には、電柱側に設置されている高圧引込線の開閉器(区分開閉器)を開放し、建物への高圧供給を遮ります。
また、建物附属のキュービクル(受電盤)内部で電力会社資産となっていた計器用変圧変流器、電力量計を外し、高圧側回路を完全に切り離します。電力会社の担当者によって高圧計器(電力量計)の最終検針も行われ、この時点で電力会社から見た高圧契約は停止完了となります。
低圧への切替えは既に完了していますが、分電盤や幹線の付け替え作業に伴い、作業中は建物全体または一部の設備が2時間程度使えなくなる場合もございます。冷凍機や通信機器の事前停止・復旧手順を周知しておきましょう。
❹後日対応
15)使用前検査【電気工事会社】
高圧設備の撤去低圧への切替が完了した後、新たに設置した低圧設備の各種試験・検査を実施します。低圧幹線や分電盤、配線工事が適切に行われ、安全に利用できることを確認する重要なプロセスです。具体的には、以下のような検査を行います。
- 絶縁抵抗測定(メガーテスト):ケーブルや機器の絶縁状態が良好であることを確認します。
- 接地抵抗の測定:アースが規定値以下の抵抗で設置されていることをチェックします。
- 機器の動作試験:分電盤内のブレーカーや漏電遮断器が正常に動作するか、非常用発電機等との連動は問題ないか確認します。
これらの検査を通じて、低圧設備が法令基準を満たし安全に使用できる状態であることを保証します。また、検査結果は所定の様式に記録し、お客様にも報告いたします。
16)PCB検査(推奨)【電気工事会社】
もしメーカー発行の「PCB非含有証明書」や分析結果報告書が無い場合、撤去した変圧器やコンデンサについて簡易検査キットによるPCB検出試験を実施します(専門の分析機関に依頼することもあります)。
仮にPCBが含まれていることが確認された場合、その機器は産業廃棄物処理業者等を通じて法令に従い適切に処理しなければなりません。現在、日本ではポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理について期限が定められており、低濃度PCB廃棄物は2027年(令和9年)3月末までに無害化処分を完了させる義務があります。
期限を過ぎると行政処分の対象となるため、PCB含有機器が判明した場合は計画的に処理を進めます(詳細は環境省のガイドライン等をご参照ください)。幸いPCBが含まれていなかった機器については、鉄くずや有価物としてリサイクル処理することも可能です。
関連記事を読む
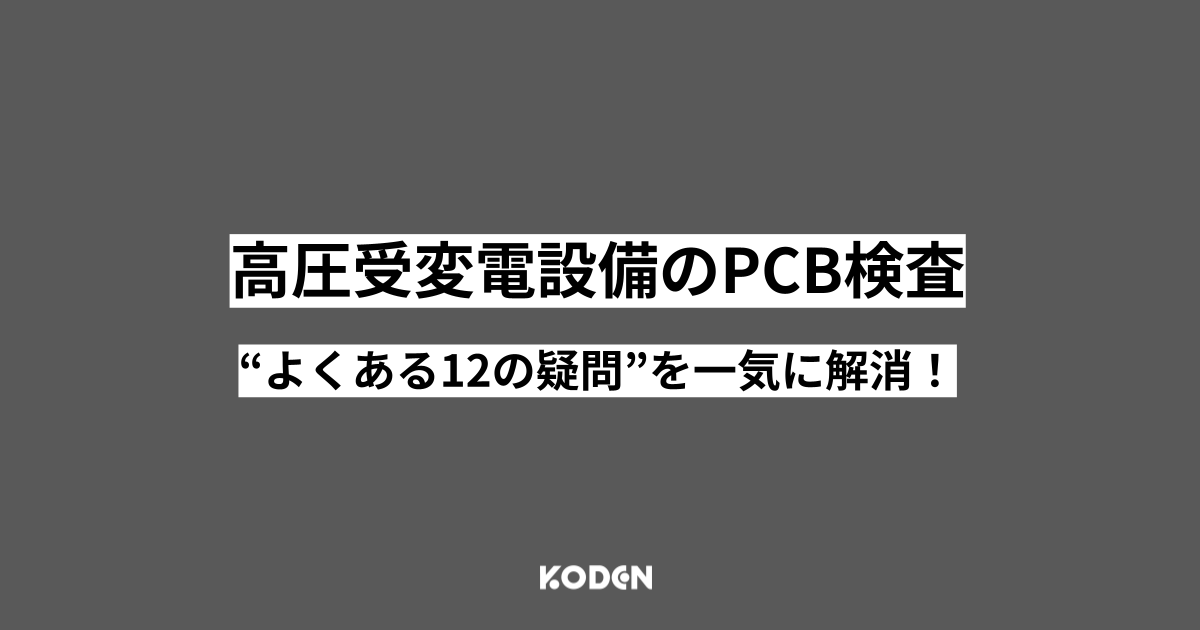
17)工事完了報告・引渡し【電気工事会社】
全ての工程が完了したことをお客様へご報告し、設備一式をお引き渡しします。低圧受電設備の図面や工事報告書、検査成績書などの書類も併せて提出いたします。
ここに至るまで長期間にわたる工事となりましたが、お客様には高圧設備に関する負担が一切無くなり、以降は低圧契約の電気を安心してお使いいただける状態となります。
18)VCT・メーター・引込線回収【電力会社】
工事完了後、電力会社側で残務処理があります。高圧受電設備の廃止に伴い、電力会社が所有していた計器類や配線の撤去です。
具体的には、キュービクル内に設置されていた計器用変成器(VCTなど)や電力メーター、高圧の引込ケーブル(電柱から建物への高圧線)といった電力会社資産が回収されます。これらの撤去作業は電力会社の担当部署が行いますが、事前連絡がある場合と訪問即時回収の場合があり、方法は指定できません。事前連絡があるケースでは電気工事会社にも連絡が入ります。
いずれにせよ、電力会社側設備の撤去が完了すれば、高圧受電に関する物理的な痕跡はほぼ無くなります。
19)工事負担金の追加請求・返金可能性【電力会社】
負担金に過不足が出た場合、電力会社から差額精算の案内が届きます。内容をご確認のうえ、追加請求時は支払期限を確認し、対応してください。
実際の工事で費用が見積りより下回った場合、お客様に返金が発生する場合もあります。返金時は振込先口座を連絡します。
20)工事費用の支払い【お客様】
電気工事会社へ、工事完了後の工事代金のお支払いを頂きます。
見積り・契約時に取り決めた支払条件に従い、請求書の期日までに指定の口座へ工事費用をお振込みください。分割払いやリース等の方法を採用している場合は、そのスケジュールに沿ってお支払いください。
21)主任技術者費用の支払い【お客様】
最後に、電気主任技術者への清算です。高圧受電を廃止するまでの期間、主任技術者(外部委託先)が定期点検や工事立会いなどの業務を行っていました。
契約解除月までの保安管理料や、切替工事日における立会い費用など、まだお支払いがお済みでない費用があれば清算します。外部委託の保安会社であれば最終月までの日割計算となることもありますし、社内主任技術者の場合でも資格手当等の清算が必要なケースがあります。
これらも漏れなく処理し、高圧受電に関連する全ての手続きを完了させます。
施工事例
まとめ
以上が「高圧受電設備の低圧化(高圧低圧更新)工事の流れ」です。
一連のプロセスは専門的で複雑に思えるかもしれませんが、信頼できる電気工事会社に依頼すれば、事前の診断からアフターフォローまでワンストップで対応してもらえます。
恒電社では、お客様の状況に合わせ最適な低圧化プランを提案し、必要に応じて将来的に高圧契約へ戻すことも見据えた設備構成を採用するなど柔軟に対応しております。高圧受電設備の老朽化や電気料金削減にお悩みの法人オーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。
高圧から低圧への更新メリットを最大限に活かし、安心・安全かつ経済的な電力利用のお手伝いをさせていただきます。
この記事を書いた人