【2026年4月1日から】変圧器(トランス)トップランナー基準改定の徹底解説:2025年9月中に企業が取るべき対応策とは?
カテゴリー:
タグ:
更新日:2025年12月24日
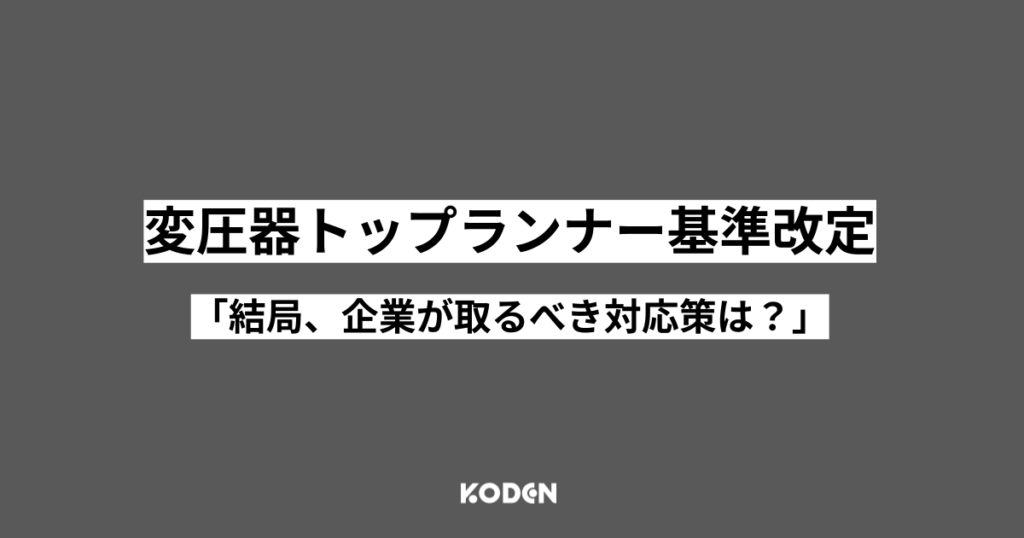
日本政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」実現に向け、電気設備の省エネ化は企業経営にとってますます重要な課題となっています。特に、工場やビルで使用される高圧受変電設備の変圧器は、24時間365日稼働するため、僅かなエネルギーロスも積もれば大きなコストとなり、企業のCO2排出量にも影響を及ぼします。
従来、2006年度以降に段階的に導入された省エネ法のトップランナー基準は、最も効率の高い製品の性能を基準値とし、各メーカーがその水準を目指して高効率製品を開発・提供してきました。しかし、現状では製造から20年以上経過した旧式機種が約57%を占め、さらなる省エネ効果が求められています。
そこで、最新技術を反映した「トップランナー変圧器の第三次判断基準」が2026年度に改定されることになりました。本記事では、改定の背景や目的、対象となる変圧器の種類、そしてメーカー・ユーザー・施工業者それぞれが取るべき具体的な対応策について、専門用語を噛み砕いてわかりやすく解説します。
目次
【要約】
1)改定理由:省エネとカーボンニュートラルの推進
日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を目標に掲げ、電力需要側での省エネ強化が求められています。変圧器は常時電力を消費する機器であり、特に製造から20年以上経過した旧式機種が約57%を占め、エネルギー効率が低いため、最新技術を反映した高効率変圧器への置き換えが必要とされています。
2)交換の必要性:直ちに義務はないが、更新が推奨される
新基準は新たに製造・販売される変圧器の効率基準に関するもので、既存の変圧器を直ちに交換する法的義務はありません。しかし、古い変圧器はエネルギー損失が大きく、経年劣化も進行するため、計画的な更新が推奨されます。
3)企業(設備オーナー)の対応:現状把握と計画的な更新の検討
企業は自社の変圧器の製造年や効率を確認し、特に20年以上経過した機器については更新を検討すべきです。新基準対応品はサイズや重量が増す可能性があるため、設置スペースや工事の制約も考慮し、専門の電気工事会社に相談して予算計画や更新スケジュールを立てることが重要です。
なぜ基準が改定されるのか?(背景・目的)
そもそも省エネ法のトップランナー基準とは何か?
まず「トップランナー基準」とは、省エネ性能が最も優れた製品(トップランナー)の性能値を基準とし、それに合わせて他の製品の性能向上を促す制度です。変圧器もその対象製品の一つで、2000年代から省エネ性能向上の基準が段階的に設定されてきました。
具体的には、2006年度(油入変圧器)、2007年度(モールド変圧器)、2014年度を目標年度とするトップランナー基準がこれまで設けられ、メーカー各社がそれを達成する高効率変圧器を開発・提供してきました。この結果、新しい変圧器ほど損失(ムダになるエネルギー)が大幅に削減され、変圧器の省エネ技術は業界全体で広く普及しています。
今回の改定の目的は?
では、なぜ今この基準を改定するのか? 背景には日本のエネルギー政策が関係しています。日本政府は「2050年カーボンニュートラル」を目標に掲げており、電力の需要側での徹底した省エネがこれまで以上に重要になっています。変圧器は電力インフラの中で常時電力を消費する機器であり、大規模な工場やビルではその損失電力も積もれば無視できません。
政府の狙いは、変圧器の更なる高効率化によって無駄なエネルギー消費を減らし、企業の電力コスト削減と温室効果ガス排出削減の両立を図ることにあります。事実、現在国内で稼働中の変圧器のうち約57%(約221万台)は製造から20年を経過した旧式機種と推定され、こうした古い変圧器ではエネルギー効率が著しく劣ります。
新基準においては、より効率の高い「トップランナー変圧器」が普及し、これら旧式の置き換えを促進されることで、大きな省エネ効果が期待されています。国のエネルギー政策方針と足並みを揃え、「トップランナー変圧器の第三次判断基準」として2026年度を目標年度に新たなエネルギー効率基準が見直されることになりました。
「誰」が何をしなくてはいけないのか?(関係者の対応)
変圧器メーカーの対応
メーカー各社は、新たな基準を満たす製品設計への移行が必須です。2026年4月1日以降は現行の「トップランナー変圧器2014」を出荷できなくなるため、それまでに製品ラインナップを新基準対応品へ切り替える必要があります。
具体的には、損失をさらに低減させたコア材料や設計手法を採用した次世代変圧器の開発・生産を進め、2026年度以降は全ての新造変圧器が改定後のエネルギー効率基準を満たすようにします。
また、メーカーは2024年10月以降カタログ等に新しい「区分名(効率カテゴリ)」を表示する義務も負っています。これはユーザーが製品の効率区分を確認しやすくするための措置で、メーカーはユーザー企業への周知にも努めることになります。
高圧受変電設備を所有する企業(オーナー)の対応
高圧受変電設備を持つ企業では、まず自社の変圧器が新基準に照らしてどの程度の効率かを把握することが重要です。現行設備を直ちに交換しなければならない法律上の義務はありませんが、例えば製造後20年以上経過した変圧器は効率が著しく低く、電気のロス(損失)が大きい傾向にあります。
このため、経年劣化や損失増加も考慮すると、古い変圧器ほど計画的な更新を検討すべきと言えます。今回の基準改定により、新しく導入する変圧器は否応なく高効率品となりますので、更新のタイミングをどこに定めるかが企業側の検討課題です。
設備担当者は、現在使用中の変圧器の製造年を確認するか、専門の電気工事会社に問い合わせを行い、予算計画や更新スケジュールに反映させましょう。加えて、新基準対応品は従来品に比べサイズや重量が増す可能性が高いと報告されています。自社のスペースに収まるか、設置工事に制約はないかといった点も事前に確認し、必要に応じて施工業者に相談することが大切です。
※更新をご検討中のお客様・これから更新のご検討を始める方は、お気軽にご相談ください
どんな変圧器(トランス)が対象なのか?(基礎知識)
対象となる変圧器の種類
今回のトップランナー基準改定の対象となるのは、簡単に言えば事業用(産業用)変圧器です。具体的には「定格一次電圧が600Vを超え7,000V以下」で「交流回路に使用される」変圧器が範囲となります。
これは多くの工場やビルが電力会社から受電する6kV級の高圧配電用変圧器(一次側6,600Vを受けて二次側に降圧する変圧器)に相当します。
形態で言うと主に油入変圧器(油浸式変圧器)とモールド変圧器(乾式モールド=樹脂絶縁変圧器)が対象です。それぞれ単相・三相がありますが、対象となる容量範囲は単相で10~500kVA、三相で20~2000kVA程度と定められています。
一般的な工場・ビルの受変電設備に据え付けられる変圧器であれば、ほとんどがこの容量レンジに収まります。また電圧条件も、高圧側は標準的な6kVまたは3kV、低圧側は100~600Vの範囲が指定されています。要するに、通常の高圧受電設備に使われる変圧器はほぼ対象と考えて良いでしょう。
対象外となる変圧器
逆に、省エネ法トップランナー制度の適用除外となっている変圧器もあります。それは主に特殊用途の変圧器です。
具体例を挙げると、ガス絶縁変圧器(SF₆ガスなどで絶縁するタイプ)やH種絶縁の乾式変圧器(高耐熱の特殊乾式変圧器)、スコット結線変圧器(三相‐二相変換用の特殊接続変圧器)、水冷・風冷式の変圧器(特殊な冷却方式を持つもの)、および三巻線以上の多巻線変圧器(特殊な多出力用変圧器)などが該当します。これらは一般のビル・工場では滅多に使われないタイプであり、特殊なケースを除き多くの企業には関係ないでしょう。
改定による影響(企業[オーナー]への影響)
現行の変圧器はそのまま使い続けられるのか?
結論から言えば、今回の基準改定は新しく製造・販売される変圧器の効率基準に関するものであり、既設の変圧器を直ちに交換しなければならないというものではありません。
したがって、現在お使いの変圧器がすぐに違法になったり使用禁止になることはなく、引き続き使用すること自体に問題はありません。
ただし注意したいのは、変圧器は経年とともに性能(絶縁劣化や損失特性)が低下すること、そして設置から長期間経過した旧型品ほどもともとの設計上の損失も大きいという点です。
前述の通り業界ではおおむね20年程度を更新の目安とする向きがあり、実際2021年時点の調査で、国に約221万台もの20年以上使われた変圧器が稼働していると推定されています。そうした旧式の変圧器ほどエネルギー消費効率が悪く、無駄な損失を多く発生させているのが実情です。従って、新基準の施行をきっかけに、古い変圧器の更新時期について社内で見直しを図ることが望ましいでしょう。
基準改定に伴い、設備更新は必要なのか?コスト負担はあるのか?
新基準そのものは既存設備の使用を強制的に制限するものではありませんが、省エネ性能向上の観点からは古い変圧器の更新を早めるメリットが大きいと考えられます。
例えば、現在の新基準トップランナー変圧器は、1980年代以前の旧規格品と比較すると約46%も損失を削減でき、2000年代半ばの製品(トップランナー第一次基準=2005年基準)と比べても約26%の省エネ効果が期待できる水準と言われています。
これは同じ容量の変圧器でも、古いものと新しいものでは消費する無負荷損や負荷損が大きく違うことを意味します。損失が減るということは、その分これまで無駄に電力を買っていた部分が減る=電気代が減るということです。
特に24時間365日通電している変圧器ではわずかな損失低減でも年間を通すと大きな節電効果になります。逆に、更新を先送りすればその間も損失によるランニングコストのロスが続くことになるため、長期的な視点では早めの高効率機器への置き換えが経済的にも有利になるケースが多いです。
もっとも、変圧器の更新にはまとまったコストがかかるのも事実です。
変圧器本体の価格に加え、交換工事(据替え工事・古い変圧器の撤去処分など)の費用も発生します。また、高効率化のために新しい変圧器は旧型より大型化・重量化する傾向があり、据付場所によってはレイアウト変更や基礎補強が必要になる場合も考えられます。加えて、工事に伴って事業所全体の停電(操業停止)が必要になるため、そのスケジュール調整も重要です。
これらの理由から「絶対に交換しなければならない状態でなければ、現状のまま様子を見る」という選択をする企業もあるでしょう。しかし、冒頭で触れたように省エネ効果による電気代削減や設備の信頼性向上(経年劣化した変圧器の故障リスク回避)といったメリットも見逃せません。特に電力料金が高騰傾向にある中では、損失削減によるコスト低減効果は、以前にも増して企業経営に寄与するはずです。
結局、企業はどうすればいいのか?
「結局うちの会社はどうすればいいのか?」に直結する具体的な対応の進め方を整理します。基準改定が公表された今から、企業として準備すべきポイントを順を追って見ていきます。
現状の変圧器の性能評価を行う
まずは自社の変圧器の現状把握から始めましょう。
現在使用中の変圧器が新基準のエネルギー効率を満たしているか、あるいはどの程度乖離しているかを確認します。メーカー名や型式、製造年次がわかれば、それがトップランナー何次基準に適合したモデルかを調べることも可能です。
2014年度基準適合品であれば比較的高効率ですが、2000年代前半以前の機種であれば今回の新基準との差が大きいと考えられます。社内の保全記録やキュービクルの銘板を確認し、変圧器の容量・一次電圧などの仕様データをリストアップすることも一手です。
新基準への移行スケジュールを把握する
基準改定に伴う市場動向として、いつ旧基準品の販売が停止され、いつから新基準対応品のみが出回るスケジュールを理解しておく必要があります。
具体的には2026年4月1日以降、メーカー各社は現行トップランナー変圧器(2014年基準適合品)を出荷できなくなるため、その時点で市場流通する新品変圧器は全て2026年基準対応モデルに切り替わります。したがって、「いつまでに交換するか」を検討する際は、このタイミングが一つの目安になります。
新基準品は製品価格が上がる見通しなので、2025年度中に駆け込みで旧基準品を調達する選択肢もあります。ただ、長期運用を考えれば最新基準品の方が省エネ性能で有利と言えます。今後、メーカーの製品ラインナップ刷新もこのスケジュールで進むため、2024~2025年にカタログが新製品へ順次更新されていくでしょう。弊社でも調査が可能ですので、お気軽にご相談ください。
自社における更新の要否とタイミングを決定する
次に、自社の変圧器をいつ更新するかの方針を立てます。前段で把握した現状性能や製造年から、緊急性の高いもの(例:老朽化が進み故障リスクが心配、損失が大きく電気代負担が重い)かどうかを専任の電気主任技術者や設備担当者と相談の上、判断することが重要です。
例えば「設置後20年以上経過」「負荷損・無負荷損ともに現行機種より大きい」などに該当する変圧器は、できるだけ早期(ここ1~3年程度)に更新計画に乗せることを検討します。一方、比較的新しく2010年代後半以降に更新済みの変圧器であれば、性能余力もあるため無理に入れ替える必要は低いかもしれません。
いずれにせよ、2026年度以降は確実に高効率品しか入手できなくなるため、遅くとも次回更新時には新基準品に切り替わることになります。そのタイミングを見据えて、「●●年頃に更新実施」など社内の長期修繕計画に明記しておくと良いでしょう。特に生産設備の定期修理や建物の大規模改修に合わせて停電作業が可能な時期があれば、そのタイミングを逃さず変圧器更新を組み込む計画とするのがおすすめです。
<結論>電気工事会社に問い合わせをしてみる
上記で方法をご説明しましたが、自社内だけで現状の把握や更新計画を立てるのは、実際には非常に困難な場合があります。特に、設備の設置環境や既存変圧器の状態、今後のレイアウト変更や基礎補強の必要性、さらには工事に伴う停電時間など、細かい点まで正確に判断するのは専門知識がなければ難しいものです。そのため、信頼できる電気工事会社に問い合わせ、現地確認やアドバイスを受けることをお勧めします。
恒電社のような電気工事会社が、実際に現地の状況を詳しく確認し、最新基準品の導入に伴う最適な工事プランや必要な改修箇所、工事費用のお見積もりをご提供しますのでお気軽にご相談くださいませ。
※更新をご検討中のお客様・これから更新のご検討を始める方は、お気軽にご相談ください
まとめ
以上、変圧器トップランナー基準の改定ポイントと、企業がどのように対応すればよいかについて、解説をしました。
今回の基準改定は、主にメーカー向けの規制ですが、実はユーザー企業の皆様にも大変身近な問題です。高効率な変圧器に更新することで、電気料金の削減や設備の信頼性向上が期待できるだけでなく、環境負荷の軽減、つまり脱炭素社会への貢献にもつながります。ぜひこの機会に、御社の設備の現状を見直していただき、計画的なアップグレードを通じて省エネとコスト削減を実現していただければと思います。
また、新基準へのスムーズな移行準備を進めることで、将来的な法改正やエネルギー価格の変動にも柔軟に対応できる、より安定した経営基盤の構築が期待できます。今回の記事が、皆様の検討の一助となれば幸いです。
【参考】
- 経済産業省 資源エネルギー庁 「事業用変圧器の新たな省エネ基準に関する報告書をとりまとめました」(2023年6月15日)meti.go.jpmeti.go.jpmeti.go.jp 他
- 本間電機工業(株) ブログ 「変圧器のトップランナー基準変更に関する重要なお知らせ」(2025年2月3日)honmadenki.co.jphonmadenki.co.jp 他
- その他、経済産業省公開資料、省エネ法関連法令・ガイドライン等。

